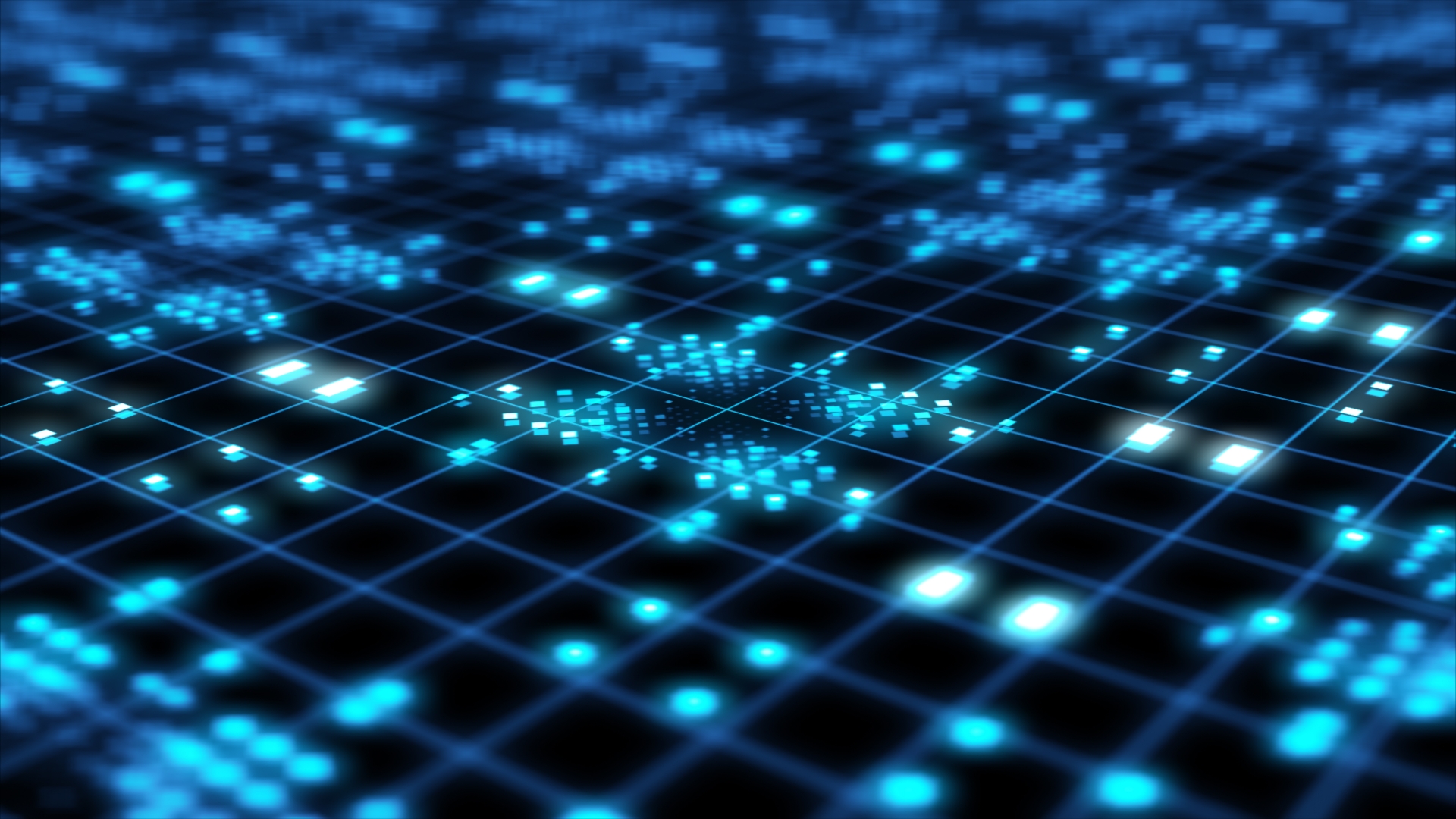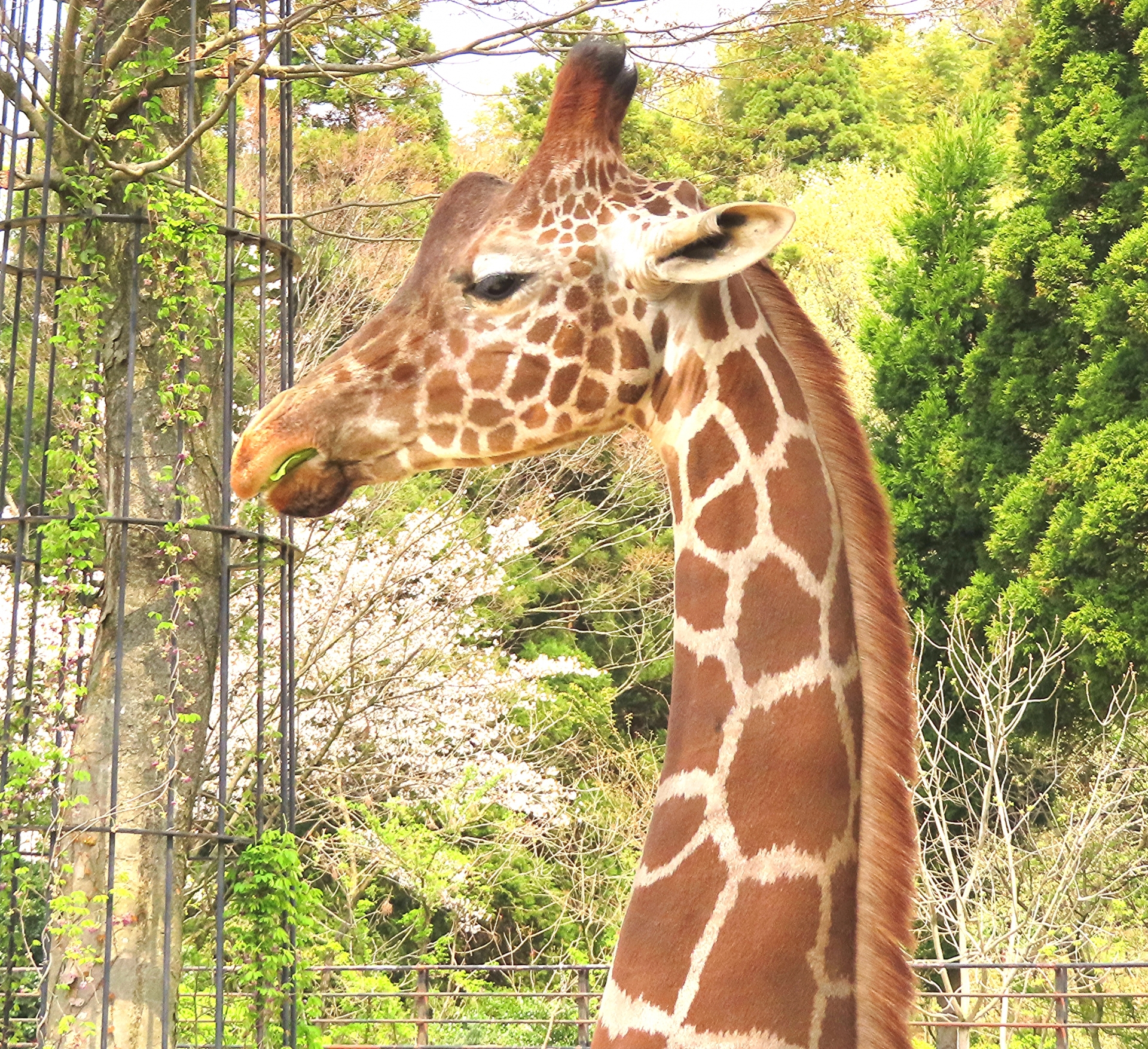UIとUX。
なぜか一部界隈では「似て非なるもの」、大同小異として一緒くたに語られがちです。
最近では、UI/UXデザイナーと名乗る人も増え、それほど珍しい職種でもなくなってきました。
しかしながら、UI(User Interface)とUX(User Experience)の間には、決して小さくない違いがあります。
例えば、毎年夏頃になると家電量販店で隣同士に並ぶ扇風機とサーキュレーターのように、多少の違いがあったとしても、似たような使用方法で特に問題ない、というモノではないでしょう。
人間の都合によって分類されているイルカとクジラや、カンガルーとワラビー(あるいはワラルー)のような、基準や境界線が曖昧になる「ややこしさ」もありません。
牛乳と低脂肪乳、乳飲料のような「売り場も近くて、よく見なければ間違える」モノでもなければ、豆乳やアーモンドミルクのように、「似ているけど全くの別物」として混同することもないでしょう。
鳥肝に付随するハツのように、たまたま近くにあって密接な関係があるからといって、「同じもの」として雑に扱えば、それぞれの良さを台無しにしてしまうリスクを孕んでいます。
つまり、本来であればUIとUXは「混ぜるな危険」の関係性だと言えます。
レバーはレバー、ハツはハツ。
明確に切り分け、各々に適切な処理を施さないと臭みが残ってしまいます。
UIとUXもまた、境目が曖昧なまま「大同小異」という理解で済ませてもよいのでしょうか?
どこで切り分ければ良いか不明瞭なのは恐らく、視覚や触覚的な要素以外も含めた広義のUIをUXと勘違いしたり、UXを矮小化する思い込みが、根本的な理由でしょう。
どこまでをUIとして、どこからをUXと考えれば良いか。
私が提案する一つの基準は、「モノ消費」の範囲内ならUI、「コト消費」に該当するならUXと考える、です。
例外も多く、抜けも漏れの多い荒い物差しかもしれませんが、これを一つの基準として様々なものを眺めてみると、少し違った世界が見えてくるはず。
今回は、UI=モノ(見えるものや触れるもの)、UX=コト(見えないもの、体験や雰囲気)という前提で、改めて色んな物を見直してみましょう。
目次
商品やサービスは、UI + UX
UXやコト消費というフレーズが出てきたのはつい最近(ただし、コト消費は1990年代後半からなのでおよそ四半世紀?)のように思いますが、実は多くの商品やサービスはUI + UX、つまりモノとコトの両方で出来ている、ということが分かってきます。
例えば、コンビニやスーパーで食品を購入するとしましょう。
UIはもちろん、店内に陳列されている商品や、店舗そのものです。UXは、店員さんの接客態度や、一緒に来店している他のお客さんを含めた、お店の雰囲気が該当するでしょう。
商品を購入後、その商品が期待通りだったか、満足したかどうかまで、UXに含まれます。
電車やバスといった公共交通機関、あるいは飛行機での移動も、UIとUXの両方が関わってきます。
列車や車両、航空機といった乗り物自体が巨大なUIですが、内部の床や座席もUIです。乗っている間のサービスや、運転技術はUXです。チケットの購入手続きや乗り降りは、場面場面を切り取ればUIも沢山出てきますが、それらをひっくるめた「利用体験」はUXでしょう。
乗り降りする場所や駅、巨大なターミナルや空港も、UIとUXが混在しています。
よって、良い商品を作ればいい、良いサービスを目指すという、「コト消費」が生まれる前からある考え方は、少なくとも半分は正解だったとも言えます。
商品やサービスの良し悪しは、数々のモノとそれに携わる人や、利用する人の中に生み出されるコトが鍵を握っているということは、UIにもUXにも注力すること自体、間違った取り組みではありません。
広く知られる工夫や選ばれる努力、根気強く売り込む姿勢もあった方が良いとは思いますが、源流はまずそこにあるというのは、間違いないでしょう。
UIとUXの組み合わせが、全体を左右する
商品やサービスを構成するUIが全く同じでも、UXによって支払う価格に対する許容範囲や、それに対する満足度合いも変化します。
例えば、マクドナルドでコカコーラ社のドリンクを注文するのと、自動販売機やコンビニ、スーパーで同じ商品を購入する場合とで、全体の印象は大きく異なるでしょう。もちろん、容量やイートイン、テイクアウトで税率が変わるという面もありますが、どんな立地のどんな店舗で購入したか、またどんな場所でそれを味わったかが変化すれば、値段の差に対する不満は消えるはず。
もう少し極端な例を挙げるなら、大手メーカーのビールを缶で購入し、自宅に持ち帰って飲む場合と、(飲酒は大抵禁止されていますが)コンビニのイートインやスーパーの休憩コーナーで、買ったばかりのおつまみをお供にビールを飲む場合と、同じブランドのビールを取り扱っている居酒屋で飲む場合とで、「支払ってもいい金額」には大きな開きがあるはず。
徐々に値段は上がってきましたが、350mlの缶ビールをスーパーやコンビニで購入しても、1,000円は超えないでしょう。スナックやおつまみを買って、1,000円前後なら「そんなもんかな」というところでは。
外食として「一杯ひっかけて帰る」なら、マジックアワーによる割引や、立ち飲みスタイルで金額を抑えたり、お得なセットを頼んだとしても1,000円前後が一番下で、お店のランクが変わったり、注文する品数が増えれば、どんどん金額も上がっていきます。それでも、一人当たり3,000〜5,000円前後に収まれば「楽しかった」と気持ちよく支払えます。
場所というUIが変化し、注文する料理という「モノ」が増えることもありますが、本質的に変化しているのは、UXの方でしょう。商品やスペックが同じでも、UXが欠けていれば、「それに支払ってもいい」と思える金額は、驚くほど下がってしまいます。
一方で、UXのみでUIが伴っていない場合も、体験に対する納得感は大きく下がってしまいます。
その典型例が、個人的にも少し難易度が高いと感じている「オンラインセミナー」です。
コロナ禍を経てリモートワークやビデオ通話が普及した今、有料無料を問わず、オンラインセミナーや交流会が盛んになっていますが、そこに登場するUIとしては、せいぜいビデオ通話アプリぐらいでしょう。
いくら「特別なセミナーだ」と喧伝されたところで、結局目の前にあるのはZoomやGoogle Meetsの画面で、背景は何もない壁か、バーチャルな背景のどちらかでしょう。中には例外もありますが、会場となる空間やシチュエーションといったUIの力を欠いた状態だと、特別感は薄れてしまいます。
そこに、印刷された講演資料や物理的なノベルティなど、何か持ち帰れるモノが用意されていれば、「これのためにお金を払ったんだな」と納得できますし、「何に払ったの?」」と問われても、「これが証拠です」と堂々と提示することができます。
参加後に主催者側から、講演資料は後でダウンロードしておいてくださいとか、SlideShareなどのURLでも送られてくるようなら、ちょっとガッカリしてしまうかもしれません。
仮に参加費が無料であったとしても、メールアドレスやSNSのアカウント情報を提供している可能性が高く、参加者は決して安くない対価を支払っています。
それにも関わらず、UIが不足していたせいで、全体として残念なUXになってしまうーーそんな事例も、決して珍しくないのかもしれません。
どれだけ内容という「UX」が素晴らしくても、満足度の高いオンラインセミナーや交流会を実現するのは、思っている以上に難しいことなのだなと、つくづく感じます。
UIとUXにまつわる例え話として、茶道のある流派の家元、宗匠が、ありがたいお話をするセミナーを開催するとします。由緒ある流派であれば、それだけでも貴重な機会となり、短時間でも高額な参加費用が想定されるでしょう。
この時点では、ほぼUXのみで構成されています。
もしそのセミナーが、特別なお茶室で開催され、宗匠や門下生によるお手前があり、お茶とお茶菓子までいただけるーーというないようになれば、参加費はさらに高額になるはず。
明確なUIとして、「お茶」や「お茶菓子」が登場し、特別なお茶室やお手前というUXも加わることで、体験全体の価値が大きく高まります。「ありがたい話」だけでも参加者は集まると思いますが、UIもUXも揃うことによって、より一層の集客力の獲得と、高額な参加費であっても納得感が強まる効果が期待されます。
茶道というテーマで、更に広げてみましょう。
例えば、野点が開催されるとします。
宗匠や門下生による本格的なお手前が披露される場合と、地元の中学校や高校の茶道部が参加する場合とでは、たとえ使われるお茶やお茶菓子といったUIが同じだったとしても、体験としてのUXの違いによって、参加費や満足度は大きく変わってくるはずです。
このように、UIとUXはお互いに影響し合い、全体の価値や印象を大きく左右します。
どちらか一方だけでは、体験としての完成度が欠けてしまい、支払いに対する納得感も得られにくくなります。例えUX(コト消費)を重視する場合であっても、「これにお金を払っているんだ」と自他に説明できるようなモノ=UIをきちんと用意しておく方が、結果的に満足度を高めるのでオススメです。
鍵を握るのは、UI
UXがどれだけ素晴らしくてもーーまたは、どんなに酷くても、最終的な印象や、支払いに対する納得感を左右するのはUIにあると感じています。
これは個人的な偏見かもしれませんが、総合的な体験として、「これなら妥当だな」と思えるかどうかは、結局のところ、目に見えるモノや手に取れるモノといったUIに委ねられるような気がします。
例えば、映画やライブ、その他のイベントへ赴いた時。
出演者の体調や会場の設営、あるいは座席の巡り合わせなどで、事前の期待を下回る「ちょっと残念」な体験になったとしても、参加者特典のノベルティや、会場限定の物販で手に入れたグッズのクオリティが高ければ、「中身はイマイチだったけど、いいイベントだった」と納得するかもしれません。
また、家族のおでかけでテーマパークやレジャー施設を訪れた際も、現場では些細なことでケンカになったり、誰かのワガママから険悪なムードに発展する場面があったとしても、一葉の素敵な写真が残っていれば、「色々あったけど、いい思い出だったね」と振り返ることもあるでしょう。
リアルタイムでの体験ももちろん重要ですが、後々まで残る「触れられるモノ」、つまりUIの存在というのは、体験全体の印象を形成する上で、非常に大きな影響力を持っています。
UIに対して不満を抱くと、全体のUXや、支払いに対する納得感も一気に悪化してしまいます。
よくありそうな例として、例えばテーマパーク内の飲食店や、レジャープールのフードコートを思い浮かべてみてください。現場の制約が多く、電気やガスのインフラが限られていたり、狭い厨房で創意工夫しなければならない必要があったりと、セントラルキッチン方式や冷凍食品をそのまま解凍、加熱するような対応になるのも、決して珍しくありません。
事情はよく分かりますし、慣れない環境で働くアルバイトっぽいスタッフの努力にも頭が下がるのですが、それでも通常より高めの価格帯に設定されたメニューに対して、注文時に電子レンジの音が聞こえたり、出てきた料理がメニューの写真とかけ離れていたりすると、選択肢がそれしかないから、長い時間をかけて列に並んだのに、という不満も相まって「あれ?」と違和感を覚えてしまっても、仕方がないでしょう。
グッズの物販でも、他でも買えそうな商品なのに、クオリティに疑問を感じるようであれば、「これにこの値段?」とモヤモヤが残ってしまうでしょう。
こういった体験を通じても、総合的なUXの印象や、支払いに対する妥当性や納得感において、UIが占める影響は決して小さくないことが見えてきます。
また、ブランドの印象を左右する鍵も、UIが握っていることがあります。
少しローカルな例になりますが、大阪の梅田と神戸の三宮の間には、阪急・阪神・JRの3路線が並走しています。京都方面の場合、阪急の四条河原町や京阪の祇園四条や三条、出町柳、JRの京都駅のように終着駅が少し離れていますが、梅田と三宮の場合、どちらもかなり近い場所に終着駅が集まっています。
海沿いの下町を結ぶ阪神、最も山側を走る阪急、その中間を走るJRーーそれぞれの路線は、走る場所や途中駅が異なるため、「どれを選んでも全く同じ」ではありません。
運賃や乗車時間といった体験の差だけでなく、どんな列車がどんな街を通り、駅周辺がどうなっているかというUIの違いによって、各鉄道に対する印象は大きく異なります。
さらに、梅田や三宮といったターミナル駅周辺にある商業施設やテナント、駅ビルの設え、デパートでの取扱商品、駅前の開発やイベント広告なども含めて、「それぞれの違い」はUIにも現れています。
鉄道に限らず、航空会社でも同じことが言えます。
パイロットの技術やCAの接客、空港での手続きといったUX自体は、JALでもANAでも大きな差はないかもしれません。しかし、機内で提供されるサービス、空港内での物販や飲食店のラインナップ、スタッフの制服や人材といったUIには、それぞれのこだわりが色濃く反映されています。
これは、LCC同士であっても、同様でしょう。
つまり、「ブランド=品質保証」という観点から見ると、その本質はUXーー目には見えない体験の質にあるとも言えますが、UXの印象を左右し、実際に「らしさ」を形作っているのは、UIが司っている部分が非常に大きい、と言えます。
「神は細部に宿る」とよく言いますし、ダンスや体操などのパフォーマンスにおいても、「指先や表情、視線が大事」とされるように、UIの細部にはブランド全体の印象を左右する力が宿っています。
顧客とのタッチポイントは、全てUI
「カスタマージャーニー」という言葉が日本に持ち込まれてから、もう何年も経ちますが、実務レベルで活用できているのは、ごく一部の大企業や専門の事業者に限られているように感じます。特に、BtoBが中心の中小企業や、BtoCがメインの街場の店舗、零細企業には、そこまで浸透していないというのが、個人的な肌感覚です。
インターネットやSNSがすっかり定着した今では、直接の顧客だけでなく、これから顧客になるかもしれない人や、無関係に思える生活者まで視野に入れ、購入の前も後も気にかける時間がどんどん長くなっています。そんな時代において、カスタマージャーニーが担う役割は決して小さくありません。
ただ、実際にはペルソナやカスタマージャーニーは作ること自体が難しく、その活用や運用面においても別の難しさがあるため、敬遠されているように思います。
それでも、UIやUXを考える上で、ラフなものでも構わないので、ペルソナやカスタマージャーニーは用意しておいた方が良いでしょう。高精度であるに越したことはありませんが、最低限「どこで顧客や見込み顧客と接点を持っているのか」が把握できなければ、気にかけるべきUIが分からなくなります。
例えば、券売機で注文する飲食店や、セルフレジで決済する小売店も、今では珍しくありません。
あくまでも商品や味、接客で勝負するつもりでも、券売機やセルフレジの使い勝手が悪かったり、バーコードの読み取り精度が低かったり、クレジットカードや交通系ICカードの読み取りに時間がかかったり、タッチパネルや端末が汚れていたりすると、それだけで全体の印象が悪くなるかもしれません。
また、テーブルに置かれた専用タブレットや、QRコードから表示される画面でメニューを確認したり、注文する仕組みも増えていますが、どれだけ商品や接客が良くても、そういったデバイスや画面上のUIの悪さが原因となって、総合評価が下がることもあります。
さらに、来店前に新商品やキャンペーンの詳細をチェックしたり、グランドメニューの価格を調べようと、公式サイトやクーポン・口コミ系のポータルサイトを見るケースも多いでしょう。そこでサイトが見にくかったり、読み込みが遅かったりすると、それもまたブランドの印象を左右します。
イベントの告知用LPや、ポスター・中吊り広告の仕上がりが今ひとつだったり、掲載場所の選定や印刷トラブルなどによって、実際の中身は素晴らしいのに、些細な印象で損をすることもあり得ます。
いわゆる食玩やお子様ランチのオマケ玩具が、あまりにも残念な仕上がりだったり、塗装が甘かったり、偶然一部が欠けたものだったりすると、それ一つで「全体的にダメだった」と判断されることもあるでしょう。
提供する側としては、「一事が万事だとしても、そこまで目くじら立てなくても」と思いますが、受け取る側にとっては常に一期一会。その瞬間が全てであり、全体の評価を左右する場面も少なくありません。
つまり、どれだけ優れたUXを提供していても、顧客とのタッチポイントでUIが整っていなければ、全体としての印象を損なう恐れがあります。
それくらい、UIというのは気を抜けません。
スタッフの一挙手一投足まで含めて、UIとして顧客から厳しくチェックされる。
分かっていても、「何から何まで気を配るのは無理だ」と思うかもしれません。
ヒト・モノ・カネのリソースは潤沢ではないし、現場は常に手一杯?
だからこそ、ペルソナとカスタマージャーニーマップが必要なんです。
ラフなもので構いません。
どこで顧客と接触するのかが分かっていれば、注力すべきUIも絞り込めます。
自社にとって重要なペルソナも把握できていれば、「何を優先するか」や、「どこなら手を抜いて良いか」が判断しやすくなります。
その結果、限られた資源でも、効率の良い対策が可能となります。
より重要なタッチポイントが見つけやすくなり、優先順位も明確になるでしょう。
UXやブランドを守るためにも、無理なくUIをブラッシュアップしていくためにも、ペルソナの作成とカスタマージャーニーの導入、タッチポイントの明確化を推奨します。
UIはモノ、UXはコト。そしてUI + UXへ
UIは「見えるモノ、触れられるモノ」、UXは「見えないもの体験や雰囲気=コト」として捉え、「UI/UXとは何か」を整理してきました。
UIやUXを単体で提供するのではなく、UIもUXもどちらも用意した方が、顧客にとって納得感のある体験が成立する——という点も、お分かりいただけたのではないでしょうか。
また、優れたUIがUX全体の評価を左右し、UXの質が個々のUIに対する印象を左右するように、両者は密接に結びついており、互いに影響し合う「入れ子構造」として存在しています。
このように理解することで、UIとUXを混同することなく、どう活用すればよいかを直観的に把握できるようになれば、幸いです。「UI/UXデザイナー」も、これで、何を見て、どう取り組めばよいかも、よくお分かりになるかと思います。
UIとUXの関係性が理解していれば、長くブランドを愛用してくれていたユーザーが、ある日突然離れてしまった理由が、商品やサービスそのものへの不満ではなく、UI上の非常に小さな瑕疵にあったーーということも、気付けるかもしれません。
また、第一印象の良し悪しや、すでに起きてしまったミスそのものより、その後にどうリカバリーするか、最後にどんな印象を残せるかの方が、ブランドやUXにとっては遥かに重要です。
もちろん、より良い商品やサービスを届け、ブランド全体の「弱い鎖」になりかねないUIの粗を無くしていくことも大切ですが、総合的なUXとしての良し悪し、そしてUI + UXという見方は、どうか忘れないよう、お気をつけください。
UI + UXなら、BBN
UIやUXへの理解は、Webサイト制作のみならず、マーケティング全体やブランド体験、さらには事業活動の根幹にまで、影響を及ぼします。
BBNでは、UIとUXを明確に切り分け、タッチポイントや体験設計まで視野に入れたWeb制作、マーケティング支援を行っています。
UI/UXデザインやペルソナ設計、カスタマージャーニーの活用など、分からないことや気になることがあれば、ぜひお気軽にご相談ください。