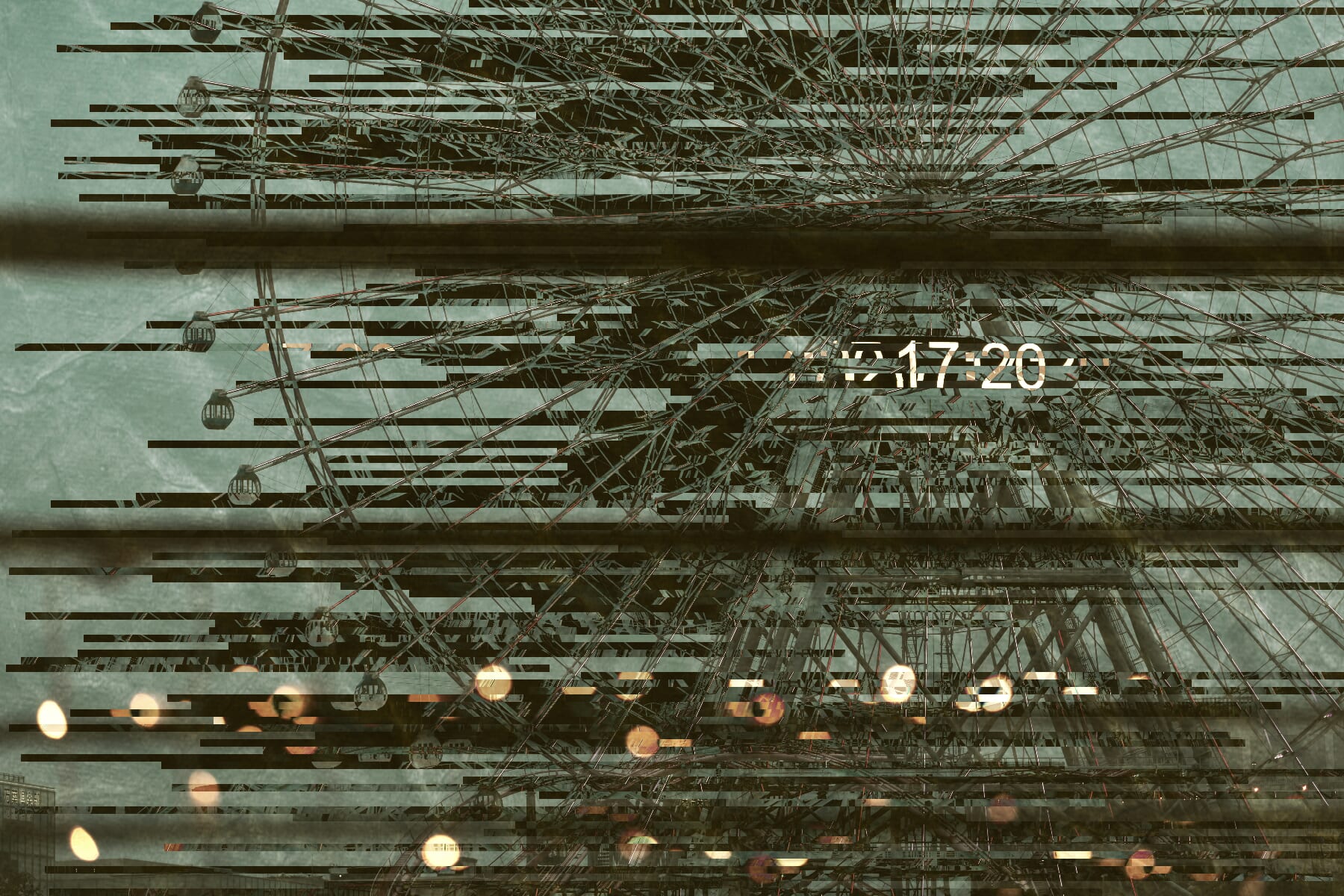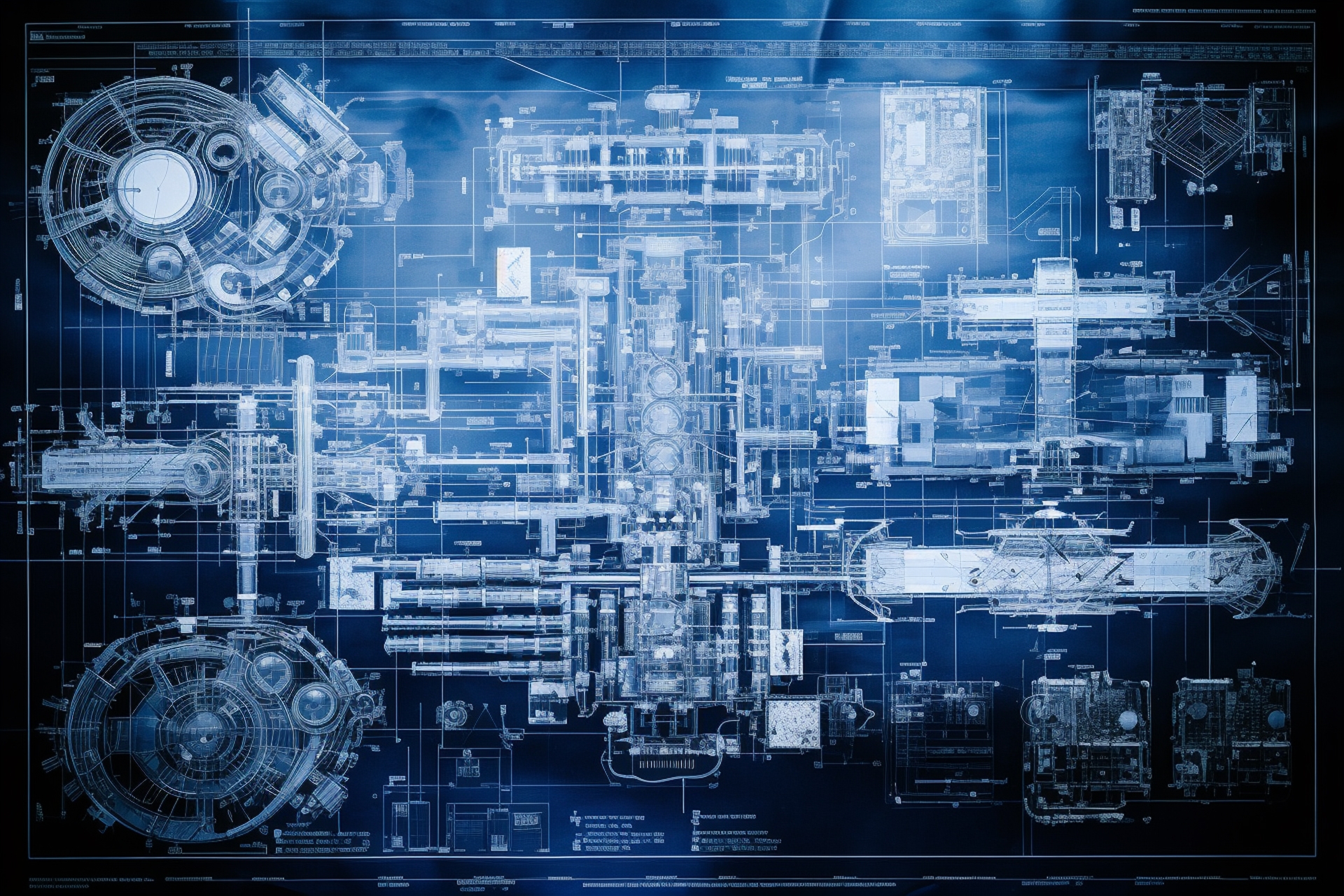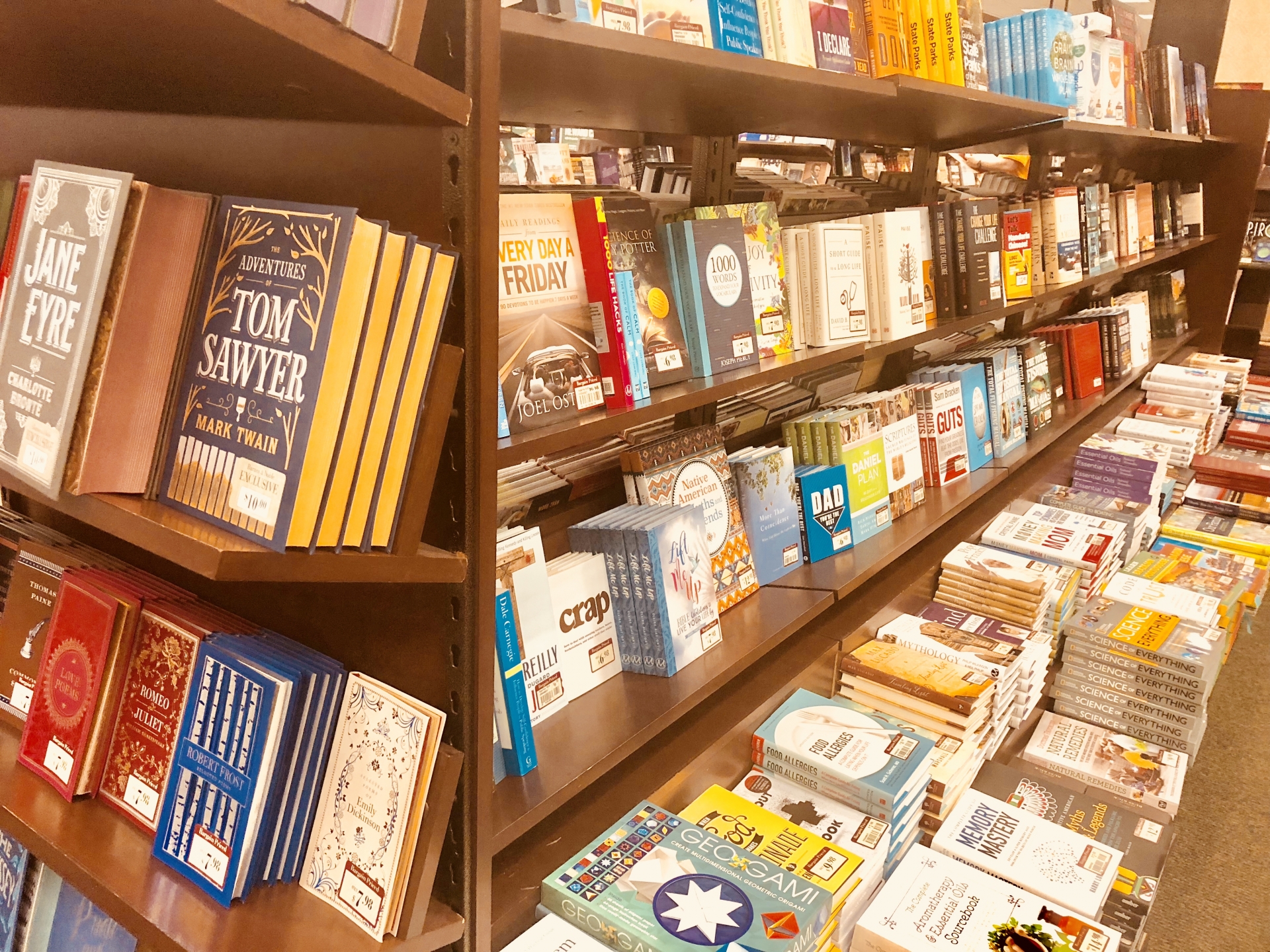先月中旬のtheLetterでは、月刊BLUEBNOSE 2025年08月号(#20)『ブランディング×悪酔いは、地獄の始まり』(https://bluebnose.theletter.jp/posts/a2f90180-726b-11f0-ae2c-f5168f194e41)と、例えブランディングであっても、「過ぎたるは猶及ばざるが如し」とやり過ぎないよう、注意を促しました。
しかし、その後に『目指せ。超ニッチなロマン技』(https://bbns.jp/knowledge/1646/) や『ギリギリ×ゾクゾク』(https://note.com/bbns/n/n600f3120fa7b)といった記事を通じて、情報発信の場面では、伝える力を最大限に高める工夫をした方が良い、ともお伝えしています。
発信する側は「これぐらいでも伝わる」と思っていても、全く思ったように伝わらないと痛感しているので、多少強めに演出しないと「何の印象にも残らない」のではという経験則からですが、情報発信の場面でも、「やり過ぎ」は禁物。腹八分目や中庸を心がけた方が良い面もあります。
端的には、単語や表現としての強さや、断定や断言などの気持ちが入り過ぎた「言い切り」がそれに該当します。そういった「強い言葉」や感情を込め過ぎた表現を使って、強く伝えましょうと提案したつもりはないので、今回はその辺りの注意喚起も含め、やはり根本的にはやり過ぎず、程々に抑えた方が良いという話をお届けします。
コンテンツを通じたコミュニケーションだけでなく、ついでにSEOについても、中庸がモアベターだということを、詳しく解説していきます。
言い切ることが大事、では?
ビジネス書、特にコミュニケーションや営業、プレゼンや資料作成のハウツーを取り上げた書籍には、「曖昧な表現を避け、言い切ること」というアドバイスが、どこかに書いてあるでしょう。
確かに伝聞調の表現や、「かもしれない」、「〜だと思う」という表現が続くと、相手や商品に対して、不安や不信感を抱いてしまいます。
つまり、「言い切ること」の持つ効果効能や、聞き手が期待する機能としては、これらの裏返し。
端的に言えば安心や信頼です。
これまでも度々、表現の自由は担保されて然るべきだけれども、そこには相応の責任も伴うと述べてきました。「言い切り」も、それを口にした人が責任を負うという暗黙の了解があるからこそ、マトモに機能すると言えます。
人は完璧ではないし、本音と建前を使い分け、嘘をつくことも可能です。
故意ではなくても、不注意や巡り合わせの結果、発言に虚偽や誤認が混ざることもあるでしょうし、無限の責任は負えないと、どこかで免責事項を掲げているかもしれません。
それでも、無責任な「言い切り」が招く混乱や社会的なリスクを避け、己の良心に則った発信をするべきでしょう。
強い「言い切り」や断言は、特に注意が必要です。
執筆に限らず、何らかの作業、特にクリエイティブな活動に取り組んでいると、だんだん筆や気持ちがノってきて、一つ一つの表現に体重や熱意がこもり、より強い快楽や爽快感を求めて、勢いのまま全力で発信したくなるかもしれません。
その気持ちは良く分かりますが、冷静さを欠き、周囲への配慮を失った強い表現は、誰かの心や名誉、財産を傷つけたり、想定外の事故に繋がる可能性を秘めています。
優良誤認や誇大広告、医療広告に関するガイドラインに関する不備程度ならまだしも、公正取引上の問題を指摘されたり、詐欺や業務妨害を問われたり、名誉毀損として訴訟を起こされてしまうと、簡単に後戻りできません。
オフレコの集まりだから大丈夫と思っていても、録画も録音も発信すらも容易な時代。
リークなどという意図もなく、どこから漏れるか、どんな速度でどこまで広まるかも予測不能です。
不用意に「絶対に〜」などの強い表現で断言してしまうと、後からどれだけ誠実に訂正や発言を行っても、社会的に受け入れられるかは微妙でしょう。
軽率な発言で炎上してしまえば、取り返しのつかないデジタルタトゥーやネットミームとして、永遠の罪になる可能性もあります。
「言い切る」時は、自分の発言に責任を持てるかどうか。発信した内容について、保証できるかを冷静に見極めましょう。強い「言い切り」や断言についてはできるだけ避けることをオススメしますが、それでも実践したい場合は、せめてその内容に誤りがないか、簡単に調べてみてからでも遅くはないでしょう。
目の前の端末で、事実の裏付けや学術論文を元に校正や校閲をかけたり、気持ちを落ち着かせてから発信すると、勢いのあまり視野狭窄に陥っていたことに気がついたり、思い込みに基づいていることも、事前に分かってリスクヘッジに繋がります。
「諸説あり」や関西人お得意の「知らんけど」でお茶を濁すのは、万能の免罪符にはなりません。
節度を保って発信すること。
また、一度表に出した表現については、しっかりと責任を持ち、誤りは適宜正すこと。
それさえ忘れなければ、言い切っても問題ないでしょう。
強い言葉、過激な表現も要注意
「言い切り」に対する注意ともよく似ていますが、単語として強い表現や、過激な言い回しも、基本的には控えた方が賢明です。
気をつけるべき理由は「言い切り」と同じですが、そもそも「雄弁は銀、沈黙は金」や「弱い犬ほどよく吠える」ということわざや、「男は黙ってサッポロビール」と昭和の名キャッチコピーがあるように、(特に男性に対して)多弁は好ましくないという社会的な風潮があります。
そこに加えて「強い言葉」を用いると、『BLEACH』に登場した藍染惣右介の著名なセリフ、「あまり強い言葉を使うなよ 弱く見えるぞ」にも通じるような気がします。
また、狭い仲間内でしか通用しない言い回しや、世間的にまだ定着していない造語といった特殊な言葉も、平気で多用されてしまうと、真剣に話を聞こうと思わなくなるのでは。
特定の人物や固有の何かを批判したり、口撃するような断罪を繰り返す人からは距離を置きたくなりますし、あまりにも力のこもったスピーチを見ると、全体主義の指導者やその代弁者めいた姿を想起させます。
それだけ、強い言葉や過激な表現には、人を遠ざける力や、発言者にネガティブなイメージを与える可能性がある、とも言えそうです。強い言葉や過激な表現は、それだけ強い力を持っている上に、小難しいテクニックも不要なので誰にでも使えますが、だからこそ「黙っていた方がいい」のでしょう。
強い言葉を並び立てて大声で騒ぐのではなく、ありふれた言葉や、時に「手垢がついた」といわれる表現を巧みに駆使し、言葉数もできるだけ抑えながら、強く深く響かせる。
これは、いわゆる「レベルを上げて物理で殴る」にも通じる、言葉の哲学です。
光の国では基本的な技とされるスペシウム光線を、必殺技の領域にまで磨き上げた初代ウルトラマンのように、熟練の職人や達人と呼ばれる人ほど、特別な道具や派手な振る舞いをするのではなく、ありふれた基本的な動きで、見事な技を披露してくれます。
本当の実力者であればあるほど、余計な言葉も装飾も不要です。
水の中を泳ぐ鯉のように、一挙手一投足が澱みなく、自然体で流れるような動きを身につけています。
その静かな佇まいが、内に秘めた自信まで醸し出すからこそ、「沈黙は金」なのです。
言葉や伝え方を磨いて、強い表現や過激な言い回しをしなくても伝えられるように、日々精進する。
その修行の一環としても、強い言葉や過度の演出は控えましょう。
素材の味を、引き算の調理でシンプルに。これが理想の情報発信です。
SEOも、いじりすぎない
内部SEOに注力しようと、特別な意味を持つHTMLタグを使いたくなってしまいますが、SEOやHTMLも、基本的にはシンプルが無難です。新しいタグや、他では使われていないHTMLを見つけると、ついつい取り入れたくなりますが、それは悪い癖や巧妙心が原因なので、避けた方が良いでしょう。
装飾に繋がるからといって、2020年代後半に差し掛かる昨今、文字を太くするのにstrongタグを多用したり、emを乱用するケースは少ないと思いますが、良かれと思ってsmallタグを使っている人は割といらっしゃるのでは。
strongタグではなくbタグを使え、という話ではなく、スタイリングとHTMLタグの関連付けをできるだけ断ち切って、太字やイタリック、文字サイズの大小は基本的に、CSSで賄った方が良いというのが基本です。
その上で、どうしてもsmallタグでなければならないとか、addressタグを使った方が良いと言った理由が明確にあるのなら、特殊なタグを使っても構いませんが、そうでないのなら、無理に変わったタグを使う必要はありません。
むしろ、Googleのアルゴリズムやスクリーンリーダーの読み上げに悪影響を及ぼしかねないので、SEOのペナルティやアクセシビリティ関連のJIS規格対応が気になるのであれば、無理をしない方がモアベターです。
特定のキーワードを無理に盛り込みすぎるな、というのも懐かしい教訓ですが、特殊なHTMLタグも同様です。ゴテゴテにいじりたくても、汎用的なdivタグやspanタグとCSSによるスタイリングで対応する。
HTML5のセマンティックなタグでのマークアップも、過ぎたるは猶及ばざるが如し。
程々がオススメです。
等身大かつ平凡に
SEOも情報発信も、身の丈を超えて大きく見せようとしない方が、上手くいくような気がします。
特殊なタグや過激な表現など、簡単に使える強化策もありますが、安易に手を出さない方がいい劇薬であり、場合によってはペナルティを喰らいかねない、ドーピングみたいな要素です。
化学調味料を使って旨味を増強したり、限界まで加工してビジュアルを強調することも可能ですが、元の味や原型が分からなくなってしまうかもしれませんし、すぐ効果が出るものに手を出してしまうと、延々とそこから抜け出せなくなる恐れもあります。
やはり、何事も程々や腹八分目、中庸、「やり過ぎない」がベターです。
無理に背伸びせず、在りのままを評価してもらう。
特殊で目立つ大技に手を出さず、地味な基礎や基本、凡事徹底を貫いて、平凡な姿で勝負すること。
自然な佇まいで、少々の変化でも狼狽えることなく、穏やかに振る舞う。
その何気ない等身大で、高い評価を得られれば、それは揺るぎない「本物」であると言えるでしょう。
SEOも情報発信も、余計な装飾も演出も必要としない素材力で、勝負しませんか?
磨くべきは、技
心技体で心も体も大切ですが、技を鍛え上げれば、強い表現も過度のSEOも要りません。
逆に言えば、技をとことん磨き上げないと、等身大の素材で勝負できません。
誰にでも真似できそうなシンプルな技で、いかにも簡単そうにやり遂げる。
どれだけ平凡に見えても、表面上を真似するだけでは上手くいかず、コツや高度なテクニックが必要となる領域にまで、基礎や基本を高めましょう。
中身が伴っていれば、余計にこねくり回す必要はありません。
中身を活かすコツを知っていれば、技も道具も最小限で十分です。
SEOや情報発信の姿勢として一番重要なのは、ビビることなく悠然かつ鷹揚に、どっしり構えることなのかもしれませんね。
職人技は、おまかせアレ
SEOも情報発信も、一見地味に思える職人技が最適解だと、個人的には考えています。
派手な奥の手や、切り札めいた秘密兵器は一切使わず、峰打ちや寸止めのような立ち居振る舞いで評価を得るには、経験や技量が物を言います。
もし、そうした職人技やノウハウが必要になったら、気軽に声をかけてください。
静かかつ揺るぎない存在感で、あなたのSEOや情報発信をサポートします。