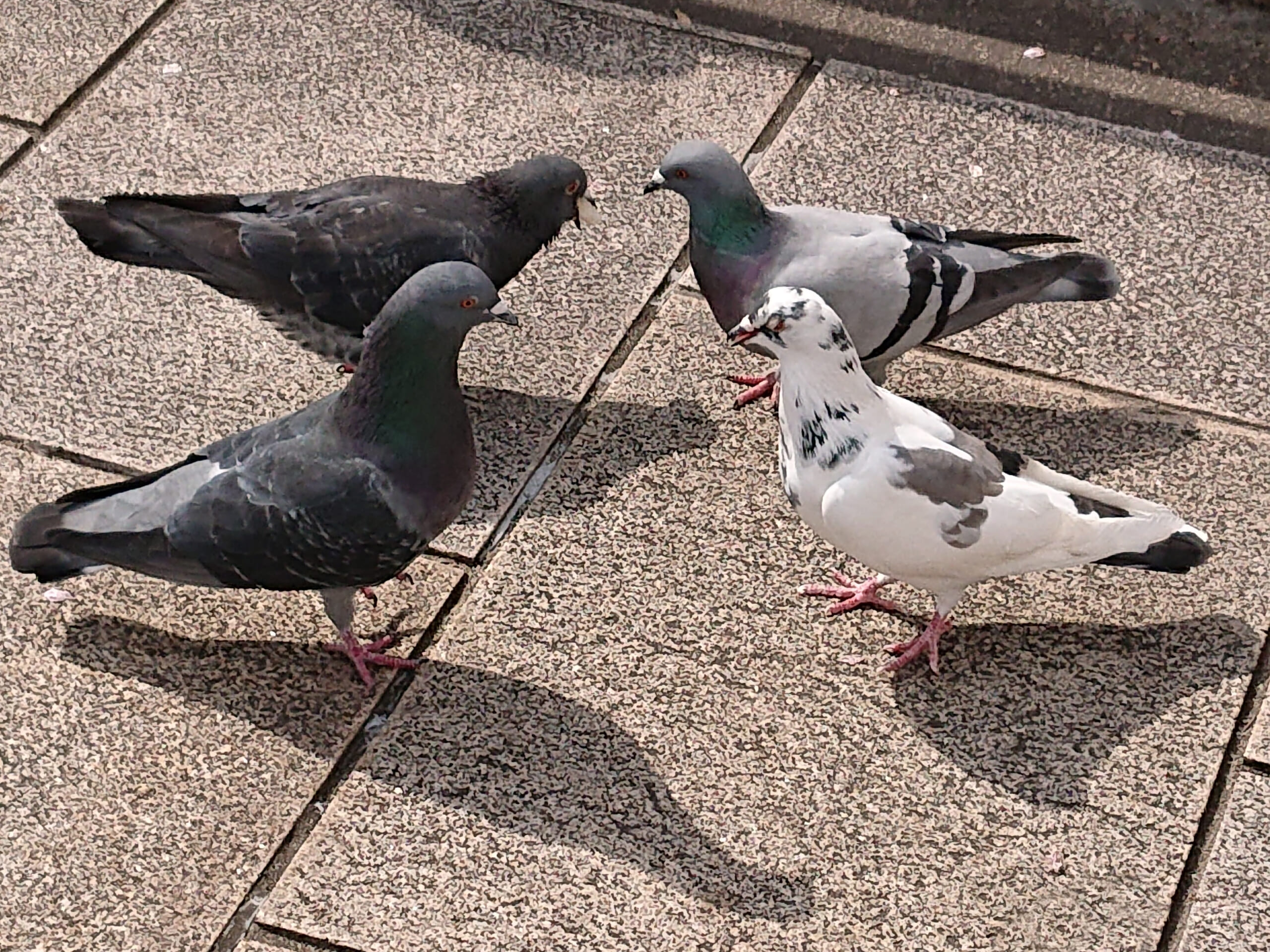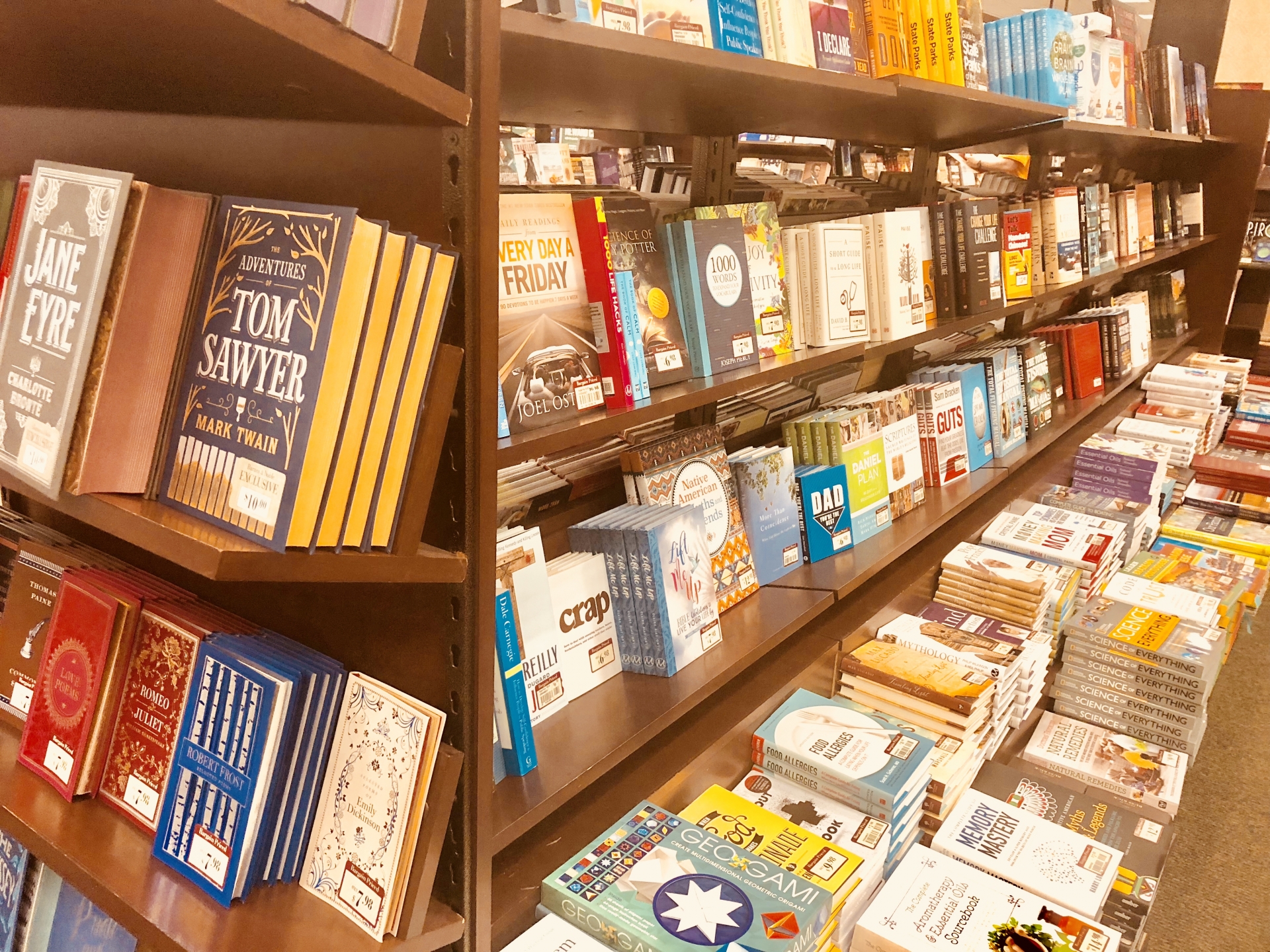2021年以来、4年ぶりに2月2日にズレた節分も終わってしまいましたね。
今後しばらくは、うるう年の翌年は2月2日が節分になるようで、暦や補正の正確さを感じると共に、必ず2月3日が節分で誕生日の象徴でもあった筆者的には、ちょっぴり寂しい気持ちもあったりします。
さて、節分が終わると今度はバレンタインとひな祭り。節分の恵方巻きや鬼のお面がついた福豆と並行して、雛あられが食品売り場の店頭に並んでいたりもしましたが、季節や行事を上手く絡めて広告宣伝が移り変わっていくのを見ると、これが日本の季節感だなとか、商魂逞しいなとか思っちゃいますね。
街中やショッピングモールなどの商業施設を歩いている最中に、そういった幟や看板を見かけても、単なる景観の一部というか、生活における一種の彩りだなと思いますが、WebやSNSで目にすると、途端に「邪魔だな」とか「気に障るな」とネガティブな印象を抱きませんか?
特に、PCで閲覧している時以上に、スマホやタブレットなどのモバイルというか、タッチデバイスで遭遇すると、京都の洛中で景観条例違反の派手な看板を見つける以上に、ネガティブな印象が増幅される気がします。これは、私だけでしょうか。
今回は、そんな「モバイルと広告」をテーマに、私の偏見を語りたいと思います。
なぜネガティブに感じるのか、そしてどうすべきなのか。偏見たっぷりで進めていきましょう。
目次
本題へ入る前に
本格的に「モバイルと広告」の話を繰り広げる前に、筆者が最近目にして気になったニュースやリンクをご紹介します。
- 世界の検索エンジン市場シェア、王者Googleが3カ月間連続で大台を割る (https://internet.watch.impress.co.jp/docs/yajiuma/1654785.html)
- ブログのPVがどんどん落ちてると思ったら、Google自体のトラフィックが1年前の4分の1になってた→「Googleはオワコン?」「AIが教えてくれる」(https://togetter.com/li/2494342)
なお、togetterの元となったつぶやきに対しては、「公式データは確認できません」という冷静なツッコミ(https://x.com/sanagi37/status/1878307811496751379)も確認しています。
Googleへのトラフィック減少と、ブログのPVに関する相関関係も不明瞭なのと、当該ブログに対して、「どんなに自信があるんだ」と突っ込みたくもなりますが、世界的なシェア低下は事実だったようなので「誤りとも言えないかも」といったところでしょうか。
ただ、「StatCounterのデータでは、Googleは日本でむしろ検索市場シェアを伸ばしている」(上記「やじうまWatch」のリンクから引用)のなら、Googleへのトラフィックだけでない影響、何かしらのアップデートの影響もあるのではとも思っちゃいますね。
そんな揚げ足取りは完全な余談ですが、モバイルファーストインデックスに切り替えたGoogleが、世界的にシェアを落として「Google検索よりも生成AI」という動きが伸びているのは注目ポイント。質の低い情報が乱立してしまい、「自然検索が死んだ」と言われて久しいこととも関連があるとは思いますが、それ以外の要因もあるんじゃないかというのが本題なので、中身へ入っていきましょう。
スクロールとタッチが同時発生してしまう
広告の中身や手法の問題へ深入りする前に、操作性の前提を改めて確認しておきます。
検索結果画面に挿入される、テキスト中心のスポンサーリンクだったり、X(旧Twitter)の投稿の間に差し込まれるプロモーションの画像主体のリンクや動画だったり、全画面表示されるタイプの物だったり。どんなタイプの広告であっても、起点となる操作はクリック=タッチやタップでしょう。
いかにして誤クリックさせるかという攻防もあり、それらを避けてスクロールしようと指を添えてしまうと、それがクリックと解釈されてしまって、広告を表示させられてしまったり、誤って音声付きの動画を再生させられてしまう、というのはよくある話でしょう。
スクロールするつもりで画面へ触れたのに、それがクリックやタッチと認識されてしまう。指を添えないとスクロールにならないのに、不可分に近いタッチを拾われてしまい、「思っていた操作ができない」と不満を募らせてしまう。
クリックを発生させずにスクロールが可能な端末と、そうではないタッチデバイスとの動かし難い差が、広告そのものに対するネガティブなイメージと、掲載している媒体への不信感を募らせる要因になっています。
画面は狭いのに、ポインターが大きい
容姿に対する言及には注意が必要なご時世で、「指が太い」なんてとんでもない話ですが、実際にタッチデバイス向けの「クリック可能な領域」の推奨幅は主に44px四方で、高さに関しては少なくとも24px程度は確保した方が良い、とされています。
「クリック可能な要素同士が近すぎ」というのは、診断ツールでよく指摘される部分ですが、1行あたり24px程度の高さならまだしも、44pxや「可能なら48px」とされているものに素直に従おうとすると、かなり広めの幅が必要になります。
要するに、マウスなどのポインターと比較すると、タッチデバイスで用いられるポインティングデバイス、すなわち「指」は、マウスほどの細かさはなく、多少太い傾向があると(特にGoogleには)考えられている、ということです。
それにも関わらず、操作対象となる画面は、マウスなどのポインティングデバイスを用いるものより狭くて小さい、となっています。2025年現在で、画面の横幅が1000px未満のPC端末は少ないと思いますが、1000pxもあるモバイル端末は希少です。
持ち運びを考慮すると、大きくてもその半分から6割ぐらいまでが一般的となると、1000px以上で最小サイズに言及がない環境と、700px未満で44pxが推奨とされる環境とで、クリックに対するシビアさがどれだけ異なるかは、お分かりいただけるかと思います。
片側二車線で、自転車用の通行帯も確保されている広い道路で自転車に乗るのと、平均台の上を前転させられるぐらいの違いはあるでしょう。目も眩むような高所で鉄骨渡りや綱渡りさせられるようなもの、と思うと怖さは倍増です。
そんな環境にも関わらず、広告を回避するための幅は狭く、広告を閉じるためのUIも小さい、注意書きもPCと比べて確認しにくい上に、誤クリックも拾われやすくて当たり判定がおかしいとなれば、ネガティブな印象が募って当然でしょう。
変な広告も多い
ちょっぴり扇情的な漫画のディスプレイが一時問題になりましたが、著名人を使ったフェイクニュースや投資詐欺、サポートを装った詐欺系の広告、著作権や商標的に問題がありそうな「SHEIN(シーイン)」、安全性に疑問符がついてしまう「Temu(テム)」といった、一見中国っぽくない名称の中国系サービスの広告など、「本当に掲載して大丈夫か?」と疑ってしまう広告も、シレッと紛れ込んでいます。
わざわざ掲載場所へ近づいて、見に行かなければ問題ないと思われそうですが、大手新聞社やマスメディアの公式サイト、検索結果画面へのスポンサーリンクなどでも見かけます。
日本国内ではMetaへの偽広告問題で訴訟が起きていますが、現在も中国発と思われる詐欺めいた出会い系広告や、大手メディアを装ったフェイクニュースの広告は後を絶ちません。
「Googleアドセンスだから問題ない」とコードを差し込み、広告収益を得るのはサイト運営者の自由ですが、その中身や、それをクリックした先の結果に対して一切責任を負わないというのは、倫理的にどうなのかと思わざるを得ません。
掲載している媒体に対しても、ネガティブに作用しかねない。「自然検索が死んだ」という事象に合わせ、検索ではなく生成AIに切り替えるのは、そういう事情も相まっているのでは。
第三者タグがパフォーマンスを下げる
広告を表示するためのコードや、広告の結果を分析するタグ、A/Bテストのための実装といった、余計な「第三者タグ」が、Webサイトの表示やレンダリングといったパフォーマンスを阻害しています。
ただでさえ回線が細い傾向が強く、通信量(つまり「ギガ」)を節約したいモバイルユーザーにとっては、「快適なWebサイト閲覧」が妨げられてしまう、悪手と言えるでしょう。
広告を表示したり、クリックさせたりすることで収益を得たい気持ちは分かりますが、それがUIやUXを低下させ、ドメインやブランドイメージまで悪化させてしまうのであれば、本末転倒です。
本当にその広告は、そこまでして表示しなければいけないものでしょうか?
「広告を表示すれば、無料で使える」からといって、その細やかな投資をケチったために、計測困難かつ多大な不利益を被っている可能性も否定できません。
PCサイトならともかく、モバイルに関してはネガティブにしかならない。
それがほぼ結論であり、Googleのシェア低下やトラフィック低下に表れているのではないでしょうか。
モバイルファーストなのに、モバイルで見る気にならない
先ほど述べたことと繰り返しになりそうですが、指やタップと広告、モバイルとの相性の悪さが原因で、「モバイルでのWebサイト閲覧は億劫だ」と感じるのは、私だけではないはず。
Google検索だけでなく、SNSの閲覧やニュースサイトのチェック、メールの確認も、余計な広告を避け、誤クリックも回避しやすいPCを利用するユーザー層が、一定数存在するのではないでしょうか。さらに、スマホなどのモバイル端末しか持たない場合は、そもそもWebやSNSすら利用せず、LINEのやり取りしかしないという人も、かなりいらっしゃるように思います。
モバイル通信環境の拡充とスマートフォンの普及によって、ユビキタス社会が実現しました。PCが主流だった時代から、個人単位で情報を届けることが可能になり、Googleもそれを見据えて「モバイルファースト」へと舵を切りました。自宅やオフィスでキーワードを入力して検索するスタイルから、出先でのカジュアルなフレーズ検索や音声検索が主流になると想定していたためです。
また、GoogleはレスポンシブWebデザインや、PageSpeed Insightsといったツールを通じ、表示速度やパフォーマンスの向上にも注力してきました。しかし、彼らの「Evilな部分」である広告部門によって、それらが阻害されている現状があります。これが、検索需要やGoogleへのトラフィックそのものの低下を招いているとも考えられます。
なんだか、地方や郊外に進出した大型ショッピングモールが、地域経済を破壊した挙句に自らも衰退し、後戻りできなくなった状況に、似ているような気もしますね。
せっかくのモバイルファーストなのに、現状のまま広告を掲載し続けると、失ってはならないものまで衰退しかねません。だから、モバイルファーストやパフォーマンス改善を真剣に考えるなら、余計な広告は掲載しないし、表示もさせない。WebサイトのUIやUXの向上と、ブランドイメージの保護も念頭に置き、広告の取り扱いをどう考えるか、しっかり検討いただけたらと思います。
ユーザーのことも、クライアントのことも考える
BBNは、Webサイトを閲覧するユーザーの気持ちや、そこから生じるクライアントやブランドへのイメージに対しても、しっかり考えた上でWebサイト制作やWebマーケティングをご提案しています。
一ユーザーとして感じるネガティブな要素、余計だと感じるものは、お客様のご要望であっても「やらない方が良い」と諫言する、「要望に必ずしも応えるとは限らない」、変なWebサイト制作をご提供していますが、そんな我々の感性や考え方に興味がある方、共感を覚えたという珍しい方がおられましたら、いつでも気軽にお問い合わせください。