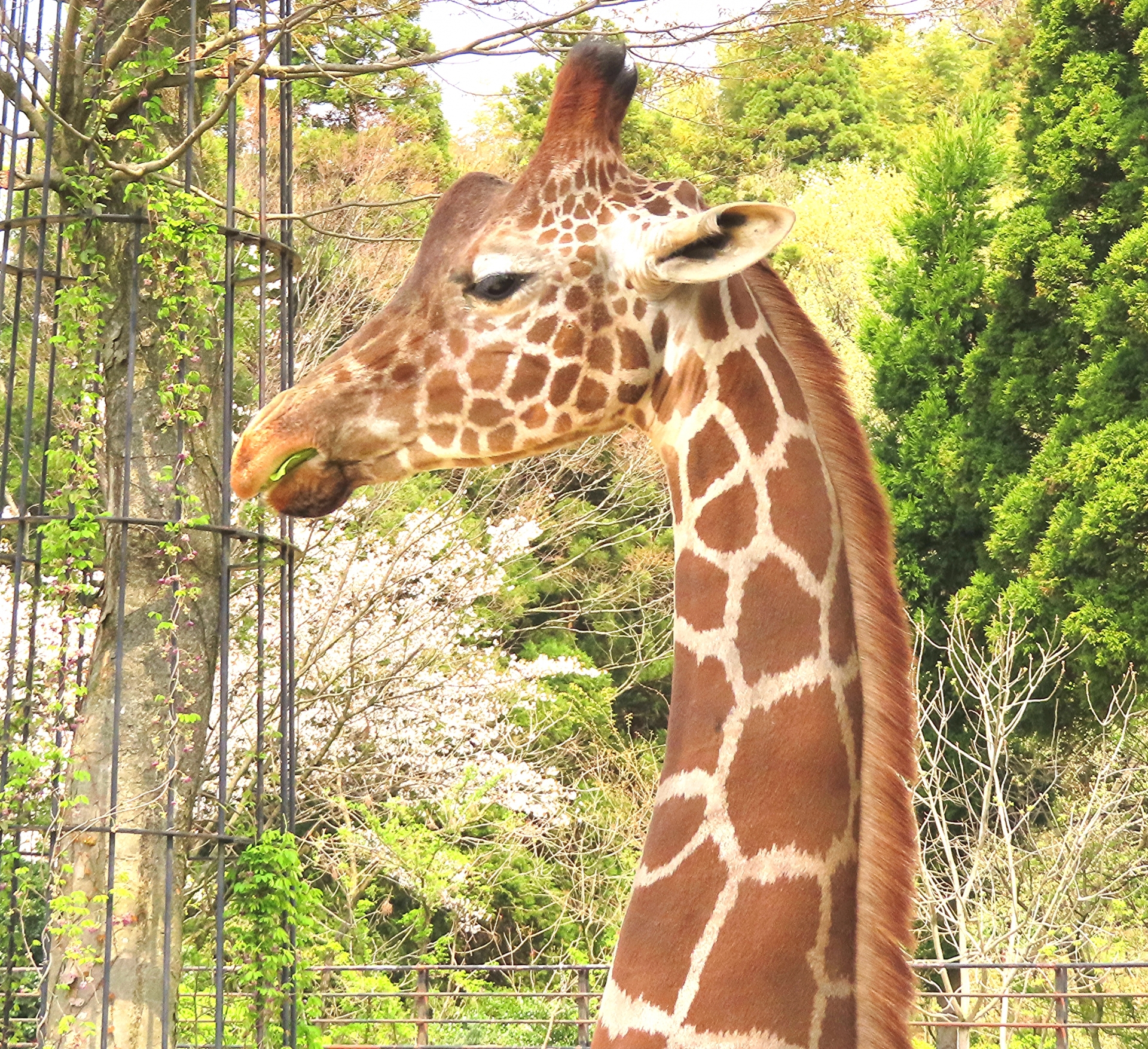あっという間に7月も中旬。新年度から新しい環境に飛び込んだ人も、新しい人を受け入れた人たちの間でも、徐々に陰口や噂話が出回り始める頃でしょうか。
あの人は仕事ができるとか、あいつはノリが悪いとか、良いことも悪いことも含めて、人の見方や評価がコミュニティの中で固まってくるのも、3ヶ月ほど経った頃からじゃないでしょうかね。
私も、6月頃の体育祭で最終学年ならクラス全員で応援合戦に参加しよう、みたいなノリに対して最後まで「自分はやらない」と突っぱねて、「なんだ、あいつ」と後ろ指を刺されてきたタイプ。どんなに懇願されても斜に構えて、仲間に入りたくないと思ってしまったり、それによって悪い評判に繋がってしまう展開というのも、非常によく分かります。
全員が一丸となって一つのことを成し遂げるという意義や、その素晴らしさも理解していますが、だからと言って、みんな仲良くとか、全員が同じ方向を向くべきみたいな思想、同調圧力で逆らえないようにすると言ったやり方には、どうしても抵抗したくなります。表向きは煌びやかに見えても、中身は教祖やイデオロギーを絶対視するカルトか、ビッグブラザーでファッショな世界観じゃん、と。
表面上はDEIだの、属性重視の多様性だのを掲げている割に、お互いの「分かり合えなさ」や中身の異質さについては跳ね除けてしまう辺り、「いわゆるリベラル」と本来のダイバーシティは「水と油」なのかもしれませんね。
さて、話が逸れ過ぎてしまいましたが、今回は「ノリの悪い人」や「考え方が合わない人」が組織に存在する意義や、グループとチームの違いについて「本来のダイバーシティ」という視点も添えながら、考えてみたいと思います。
目次
みんな同じは絶滅を招く
いきなり「組織」の話を飛び出して、生物や遺伝学の話になってしまって申し訳ないのですが、私たち人類が、男と女という2つの性を持ち、地球の隅々にまで生息域を広げてきたのは、進化の過程で手に入れた生存戦略の結果です。
生まれた場所に留まって、細胞分裂や単為生殖、つまり面倒な恋愛も求愛行動も、面倒なコミュニケーションも一切必要としない、楽な増え方が可能です。要するに、全員が同じ遺伝子を持つクローンになるということ。同じライフサイクルで行動し、同じ場所で生活し、同じタイミングで生殖して、同じタイミングで死んでいきます。
例えば、ソメイヨシノがまさにそれです。
接ぎ木などでしか増えないクローンのため、毎年いっせいに咲いて、ほぼ同時に散っていきます。ソメイヨシノ自身は、繁殖を考える必要のない品種のため、別にそれでも不都合はありませんが、もし人や野生動物が同じ状況だとどうでしょう。
同じ種の中で発情期も出産日も完全に一致し、同じ周期で生まれ、同じ周期で死んでいく。それも一箇所に固まって。攻撃したい側にとって、これほど楽な相手はいません。その「攻撃」は捕食者に限らず、気候や病原体、突発的な環境の変化という形で襲ってくるかもしれません。
全部が同じ弱点を抱えてしまうと、ある日突然絶滅しかねない。
それを避けるために、生き物は遺伝子のバリエーションを大幅に増やす仕組みを獲得しました。それが男女という性別であり、有性生殖という手間のかかるプロセスです。多様な生物を通して、地球全体、あるいは宇宙全体を通して、命を絶やさない、遺伝子を尽きさせない方法を作り上げています。
住み慣れた場所を離れ、全く別の土地へと移住する。これもまた、「みんなと同じ」からはみ出た個体の行動です。群れから弾き出されてしまった個体や、自分の住処を確保できなかった個体、伝統に馴染めず逆らいたくなってしまった個体や、強い好奇心を抑えきれなかった個体。そういった「弱い個体」や「異端児」がアフリカを出て、やがてアジアやヨーロッパ、時には海を渡って地球をほぼ一周し、南北アメリカ大陸まで辿り着いています。
これも広い目で見れば「生存戦略」です。
ずっと同じ場所に留まり続ければ、数を増やすことも、突然の変化に耐えることもできません。逃げる先も確保されていなければ、そのまま種全体が絶滅してしまいます。いざという時に他の環境へ移ったり、異なる地域に散らばっていれば、どこか一カ所がダメになっても他が生き残ってくれる。つまり、種全体としては生き延びることが可能です。
「みんなが同じ」は、安定しているようで、予期せぬ緊急事態には極端に弱いというのがよく分かりますね。
そして今はVUCAの時代。予測困難で、既存の因果や前提をひっくり返すブラックスワンは、突如、理不尽に襲いかかってきます。そんな非常時にだけ「変わり者」や「異質な人材」に頼ろうと思っても、集まってはくれないでしょう。
彼らの大半は警戒心が強く、こだわりも強い上に、頑固者であることが多いです。人見知りで、知らない相手に対する不信感も強く、性根が素直ではない捻くれ者も多いので、急な呼びかけに対しては「アンタらで勝手にやりなよ」と突っぱねるでしょう。
スーパープレイヤーでも「全員同じ」は強くない
極端な話をし過ぎかもしれないので、もう少し身近な話を取り上げましょう。
アメリカンフットボールを描いた漫画『アイシールド21』(原作:稲垣理一郎 作画:村田雄介 集英社)には、作中屈指の悪役として金剛阿含というスーパープレイヤーが登場します。彼は、『100年に一人の天才』と呼ばれ、人間における限界値とされる『0.11秒』で反応できる規格外の存在です。
そんな彼は自分が天才であることを自覚しているため、「俺が22人いりゃ、それがドリームチームだ」と豪語します。しかし、それに対して主人公チーム「泥門デビルバッツ」の司令塔、蛭魔妖一は「同じコマ22枚なんてチームほど ぶっ殺しやすいカモもねえわなぁ」と切り返しています。
格上である神龍寺ナーガに対し、一芸だけの寄せ集めに近い泥門デビルバッツは勝利を収めています。
「それもフィクションの話でしょ、都合が良すぎる」というご意見もよく分かります。
しかし、全員が同じ能力を有していて、同じ思考をするのなら、ポジションが異なる意味はあるのでしょうか? 確かに、役割が同じで左右が異なるだけというポジションもありますが、全員が同じことを考えて、同じように動くのであれば、役割分担やフォーメーションは意味を成さないでしょう。
例えば、野球の「レフト」と「ライト」。どちらも外野守備で、センターの左右に位置しています。立ち位置は異なりますが、役割は同じに見えるかもしれません。しかし、両者が「自分がボールを取って目立ちたい」と同じ打球を同じように追いかけてしまったら、どうなるでしょう?
同じものに意識が向きやすく、得意なことも関心があること、考えることも同じとなれば、物理的な視野角での死角や、思考の盲点も同じになり、フォローやカバーリングも機能不全に陥ります。これでは、別々のポジションへ配置する意味はありません。
センターや内野との連携を意識しながら、打者やランナーの動きにも気を配り、場合によってはどちらかが裏方に周り、お互いに見えていないところ、気にしていないところ、不得意なところを補い合い、自分に託された役割を果たすからこそ、ポジションやフォーメーションに意味が生まれます。
どのポジション、どの役割も卒なくこなせる天才で、なおかつユーティリティなスーパープレイヤーだったとしても「全部できる」からこそ、「そのポジションならでは」の役割に徹することができず、やりたいように振る舞ってしまうでしょう。だから、一芸だけに秀でた「そのポジションしかできない」スペシャリストの寄せ集めが、神龍寺ナーガや金剛阿含に勝ってしまう。
例えどんなスーパープレイヤーであっても、「全員同じ」は案外脆い。
そして、一見バラバラに見える異質な集団の方が、一つの目的に向き合った時には強くなる。ここに、「グループ」と「チーム」の違いが現れているようにも思いませんか?
俺が22人は、グループであってチームじゃない
ただ人が集まっただけでは、集団やグループにはなっても、チームになるとは限りません。
同質の人、似たような能力で同じ役割に向いている人、同じ趣味嗜好の人が沢山集まっても、それはただのグループでしょう。例えば、金剛阿含のようなワイドレシーバーやクォーターバックがたくさん集まって1チーム分の22人になったとしても、他のポジションに適した人が入ってこなければ、チームとしては成立しません。
野球だったら、全員が全員、「ピッチャーで四番」をやりたがるかもしれません。あるいは、「四番サード」に憧れるかもしれませんが、誰かがファーストに入ったり、キャッチャーマスクを被ったり、七番や八番打者を引き受けないと、試合ができません。
高校野球や草野球レベルなら、ピッチャーも打者も、代走要員も全部できるかもしれませんが、プロのレベルになると、両立できるのは大谷翔平ぐらいであって、その大谷翔平でも一試合で、野手も捕手も全部はできません。
また、「野手」と一括りにしても、内野と外野で求められる能力が異なりますし、内野は内野で、外野は外野で各ポジションでの向き不向きも、それぞれ異なります。
例えば、内野より守備範囲が広い外野手の場合、足は早い方が良いでしょう。どちらかというとライナーのゴロよりはフライの捕球が得意で、正確な送球より肩の強さ、強くて早い送球が求められるでしょう。
内野手の場合、打球に対する反応の速さやエラーの少なさ、正確な送球の方が優先で、フライよりはゴロがメインでしょう。外野手レベルの強くて早い送球は、ファーストの負担になるかもしれません。
また、左打席の方がファーストに近いからといって、九人の打者が全員左バッターという訳にも行かないでしょう。右利きの方が多いからといって、右投げのピッチャーばかりというのもバランスが悪く、投球スタイルや球種もバラバラでないと、バッテリー対バッター間の得意不得意もなくなります。
アメフトのようなコンタクトスポーツは、デカくて重くて強い身体だけが正義に見えるかもしれません。フィジカルの強さがものをいう場面も多いですが、小柄で軽い選手はその分スピードに優れ、ラインがこじ開けた小さな隙間でも走り込めるでしょう。地味で印象に残りにくい選手は、ディフェンスのマークを外し、相手の裏を掻いたキラーパスを受け取るチャンスに恵まれるかもしれません。
つまり、異質な人が増えれば増えるほど、戦術の選択肢が一気に広がります。どこからどう崩してくるか読めないチームに対して、相手は常に臨機応変な対応を迫られます。競技においては、「相手が何をするか分からない」こと自体、最大の強みになり得ます。
逆に、「俺が22人いれば勝てる」場合、攻略方法が確立されてしまえば、二度と勝てなくなります。得意なパターンは限られており、十分な対策を練っておけば、どこかのタイミングで必ず無力化するでしょう。
単純な一点突破は弱者に有効な戦略ですが、それは選択肢やリソースが限られていて、なおかつ「再戦」の可能性がない場合に限定されます。局地的に相手に勝ったところで、それが情報共有されてしまい、「初見殺し」の優位性がなくなってしまえば、十分に準備ができてしまう強者が有利です。
ビジネスの場合、仮に一回勝てたとしても、何度も何度も繰り返し競い合うので、戦術や選択肢、変化が少なければ、それに対応する側にとっては「楽な相手」になってしまいます。同質性にこだわってしまうと、自分たちの寿命を縮めてしまうかもしれません。
話が横道に逸れすぎましたが、チームにとって重要なのは、一つの目的や目標に対してお互いがコミットメントすることであって、各々が同じ価値観であるとか、一緒にいて好意を持てる相手かどうかは、二の次、三の次となります。
むしろ、求められている役割に応じて、適度に違っていること、またチームのメンバーに対して客観的な評価を下し、何が得意で何ができないのか、またそれによって自分はどう動いた方が良いのかを、冷静に判断できるぐらいに、感情抜きにドライに向き合えている方が、チームにとっては大きなメリットとなるでしょう。
「好きだから」とか「気が合うから」とか、「考え方や優先順位が一致する」といった感情的、感覚的な繋がりで安心して集まる集団は、ただのグループです。各々に求められる役割や仕事が明確ではなかったり、集まる意義や目的、目標が曖昧なままでは、「チーム」とは呼べません。
「何が出来るか」、「どうやって貢献してくれるか」、そしてそれにしっかり応えてくれるという信頼関係が重要なのであって、それ以外はむしろバラバラな方が、多様性に富んでいて強いかもしれない。だから、ノリの悪い人も考えの合わない人、むしろ場違いに思えるぐらい嫌いな人がいた方が、チームも組織にとっても大きな強みになるはずです。
違う方向や、違うものを見ることの大切さ
チームというキーワードが出てきたので、一風変わったチームについても触れておきましょう。
それは、「レッドチーム」。レッドチームとは、徹底的な反対意見を述べる「悪魔の代弁者」であり、組織のトップや組織の判断に対して、容赦なく攻撃を浴びせる「仮想敵」を指します。
組織の中に存在する「ノリの悪い人」や「意地悪なお局さん」のような、「何でそんなことを言うの?」と色んな人から嫌われている存在も、若干似ているような気がします。
みんなと違う方向を向いているという点では、両手の親指や野球のキャッチャーも同様です。
親指が他の4本とは異なる方向に曲がるから物が握りやすく、ピッチャーとキャッチャーが向かい合うことで初めて、野球が成立します。誰もやりたがらないからといって、キャッチャー不在で試合をしてしまえば、球を受ける役割もホームベースをカバーする役割も、野手の守備位置を確かめ、全体を広く見る人もいなくなります。
同質性や同調圧力が高くなると、組織はリーダーを頂点とするイエスマンのピラミッドに陥ります。全員が似たような価値観で行動し、似たような考えに囲まれる安心感から、自分たちの行為や考え方について、疑問を持たなくなります。
そこに対して「本当に問題がないのか」を客観視して、徹底的に盲点や痛いところを指摘します。組織が間違った方向へ進まないように、あえて異論をぶつけ、潜在的な問題や思想の誤りを正していく。積極的に嫌われにいくのが、レッドチームの役割です。
そして、そのレッドチームの攻撃を「組織のためにやってくれている」と受け止められなくなった時点で、その組織からは異質で優秀な人材から静かに離れていきます。トップが、自身の立場やプライドを守るために「あいつの考えはおかしい」と異論を切り捨てるようになると、組織はリーダーの器以上に育つことはなくなります。
リーダーが自分だけの「オレの組織」を超えて、「みんなの組織」へと変革していくためには、あえて自分とは考えが合わない人、全く理解できないぐらい異質な人をNo.2に据えるぐらいの覚悟が必要です。
考えが全く合わない人を招き入れ、チームや組織の中核となる「リーダーの想い」を、組織全体で共有可能な理念へと言語化、抽象化する作業を経ておかないと、「リーダーと組織」の分離が不十分なまま突き進むことになります。これは、リーダーよりリーダーに相応しいかもしれない優秀な人材を受け入れて、強烈な揺さぶりをかけないと、実現困難な作業です。
この通過儀礼を経ていないと、リーダーの思想に沿わない人物は排斥されるようになり、やがてリーダーの考えが絶対視されるように変化していきます。やがては「見たいものしか見ない」立派なカルト集団へと行き着くでしょう。
ダメになっていく組織、成長せずに消えていく組織というのは、組織の内側と外側、それからトップである経営層とボトムである現場の双方向の健全かつ建設的なコミュニケーションが阻害され、内向きになって硬直化する傾向にあります。リーダーの思惑から逸れた批判や建設的なフィードバック、客観的な意見や事実ですら、「攻撃」と受け止めるようになってしまえば、救うことは困難です。
おまけに、優秀な人というのは大抵の場合、自分なりの考えやスタイルを持っています。自分自身の経験やノウハウを活かし、独自性の高い創意工夫や発想を持っていることもあるでしょう。そうした人物が、「リーダーの思想が絶対」みたいな組織に、いつまでも関わってくれるでしょうか。
何度か諫言や忠告を試みても、やがて「自分がここでできることはない」と考え、そっと離れていく。やがて、リーダーより優秀な人が関わることも減り、前に在籍していた人より優秀な人が現れることもない負のループに陥る。そうすると最後は、仕事ができるかどうかも分からない、イエスマンが集まるだけのグループへと堕ちていく。
ノリが悪い人、斜に構えている人を「合わないから」という表面的な理由だけで切り捨ててしまうと、組織全体が崩壊してしまう恐れも。仮にその人がNo.2と言えるほど有能な人材でなくても、組織を繋ぎ止める「扇の要」かもしれませんよ。
別働隊、Bチームも組織を助けるかも
一見、何をやっているか分からない異端児集団が、実質的な別働隊や、いわゆるBチーム的な貢献をもたらしてくれる可能性もあります。メイン事業とは異なる分野で、次の柱となる新規事業開発のきっかけになったり、研究開発を進めてくれているかもしれません。
もちろん、「組織やチームのために」というお題目は不可欠ですが、それさえ踏襲しているのなら、誰かの指示がなくても、勝手に好き放題やってくれていることが、組織が窮地に追い込まれた際の、強烈な保険となる可能性はゼロではありません。
むしろ、外野が「ああしろ、こうしろ」と指図する方が、パフォーマンスを下げてしまうでしょう。干渉せずに、ただ見守るのがベストです。
だから、アナタが理解できない相手であっても、その裏では何をやっているかまでは分かりません。
「組織のために」と関わってくれているのなら、たとえ「みんながやっているんだから」と主要事業に協力してくれなくても、ノリが悪くて付き合ってくれず、斜に構えるようなことがあったとしても、それを直ちに「協力的ではない」とか「建設的な態度とは言い難い」と断罪するのは、本当に真っ当な向き合い方か、ちょっとだけ立ち止まって考えた方が良いのでは。
ノリが悪いも、斜に構えているのも、内面の多様性
体育会系的なノリについてこない、「ノリが悪い」人がいても、その人は簡単にノせられないことで、組織に冷静な視点をもたらしているかもしれません。いつも斜に構えていて、「なんか付き合いが悪い」人は、見えないところで努力していて疲れているだけかもしれませんし、本人はもっといいアイディアを持っているけど、理解されないと判断して口に出さないだけかもしれません。
そういう人たちに対して、「建設的な関わり方をしようよ」と呼びかけたり、自分で立場を悪くしているだけなのにと、勝手に断罪するような行為はNGです。
アナタと考えが合わない人、モノの見方が合わない人、理解できそうにないどちらかというと嫌いな人も組織内にいるからこそ、そのグループはチームとなり、チームは組織となって存続ができています。一人一人がどんなに優秀であっても、全員が同質だったり、同じ方向を向いていたり、同調圧力が強すぎるようでは、組織として簡単に打ち倒されてしまうでしょう。
組織やリーダーとして重要なのは、どれだけ異質な人を許容できるか。自分の理解が及ばない人、能力が高くて乗っ取られるかもしれない可能性がある人物を、自分の部下として信頼し、右腕とできないうちは、その組織はリーダーの器を超えられませんし、必ずどこかで頭打ちします。
質が異なる異質な人、内面の多様性を受け入れて、本来のダイバーシティ(考え方や価値観、モノの見方やスタンスの多様性)を組織の中に取り入れましょう。表面的な属性だけの多様化より、はるかに意味がある多様性です。
もちろん組織やチームとしては、サービスやブランドを通じて仕事の品質を揃えるためのガイドラインや、行動指針やポリシー、コーポレートガバナンスを設定して、外向けのアウトプットについてはある程度揃える必要があるでしょう。また、組織やチームとして達成したいこと、それに対する意欲の高さも、ある程度同じ方が安定しますが、それ以外の部分、個人の思想や内面、振る舞い方については各々の自由、自律に委ねた方が良いでしょう。
なんだか、レッドだの、ティールだののややこしい組織論にも抵触しそうですが、この話はこれ以上深掘りしないで引き返しておきます。
ノリの悪い人がいるからこそ、組織は強い。リーダーや組織の理解力、狭まっていませんか?
はぐれ者のBBN
組織に馴染めず、集団から弾かれてしまったはぐれ者が、必ずしも落ちこぼれとは限りません。
「頭の固い組織」に見切りをつけて、「一人でやってやる」と様々な課題を解決してきた強者中の強者である可能性も秘めています。
BBNは、そんなはぐれ者が作り出したサービスです。抜群に優秀かどうかは分かりませんが、十年以上、自分たちの実力で生き残っている生存者です。ステゴロで培った経験やスキル、アドリブ力を持つ我々と、Webサイト制作やマーケティングに取り組んでみませんか?
王道のやり方から、ちょっとダーティな裏技も、必要とあれば幅広く対応させていただきます。
どんな形であれ、本気で「勝ち」にこだわりたい方がいらっしゃいましたら、ぜひお声掛けください。