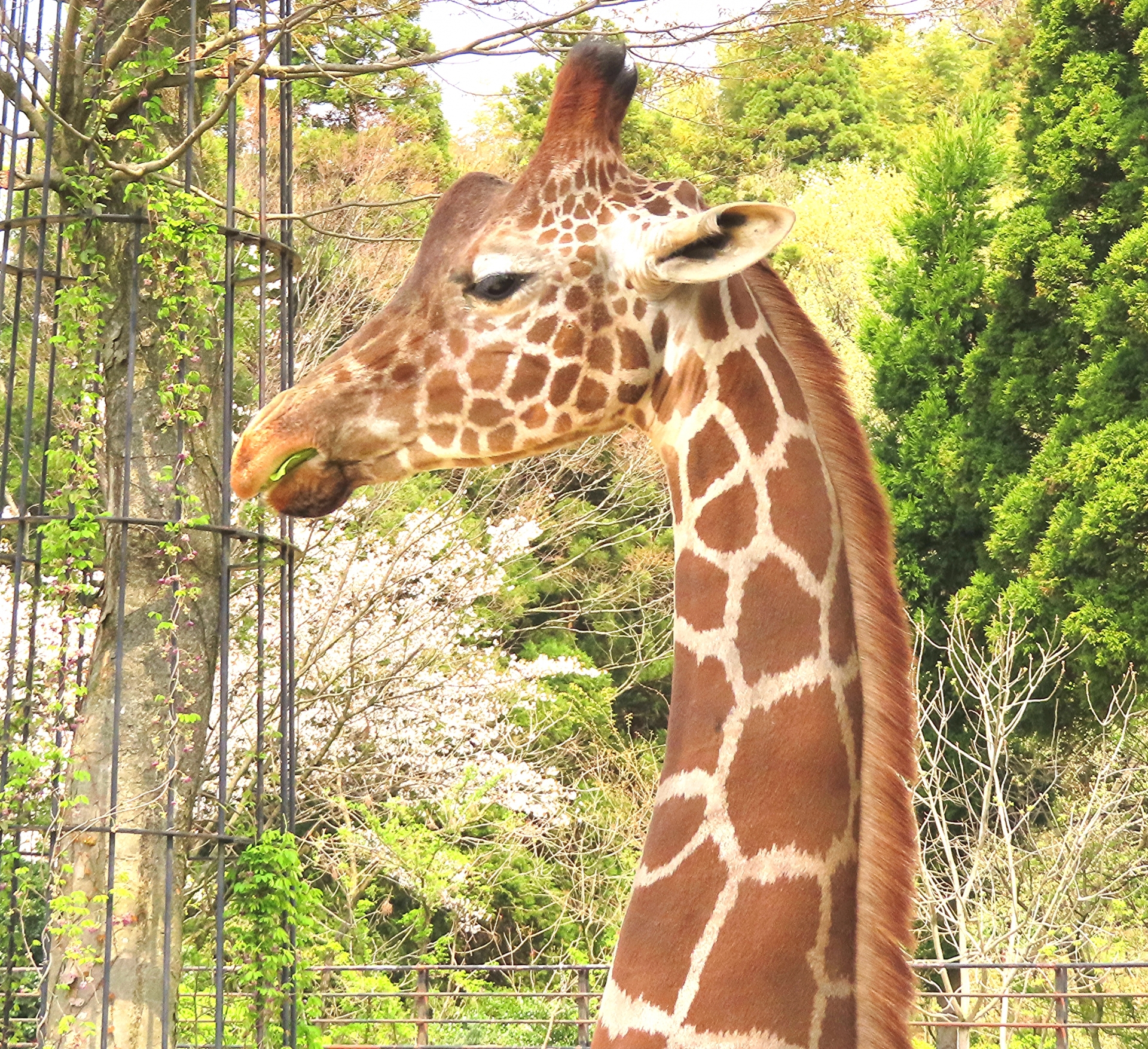目の前に、食べる前から「絶対に美味しい」と分かる料理と、口にしてみないと味が想像出来ない未知の料理があった場合、アナタはどちらを選びますか?
私なら、どちらも高額だった場合、前者を選ぶと思います。逆に、その価格や料理人を信用して「大外れしないはず」と、思い切って博打に出るかもしれません。
コンビニやスーパーマーケットでは、毎週のように新商品や期間限定フレーバーが登場します。
また、情報番組やSNSのタイムラインを通じて、新規オープンの情報や新たなキャンペーンなど、自らが街に繰り出し、足で稼がなくても、様々な情報が飛び込んでくる時代です。それに対してアナタは、どれだけ踊らされやすい消費者でしょうか?
今月配信のSubstack(https://bluebnose.substack.com/p/bluebnose-20251021)でも、ミャクミャクがいつまでも受け入れられないと「酸っぱい葡萄」を貫くよりは、新しいものを受け入れ、一緒に踊る方が良いのではという話をしています。
阿波踊りで使われる有名な掛け言葉、「踊る阿呆に見る阿呆 同じ阿呆なら踊らにゃ損々」。
アナタは”Shall we dance?”と誘われても、頑なに断るタイプですか?
かくいう私もどちらかというとノリが悪いタイプで、損してきたことも数知れず。
意固地に我を貫いたため、場を白けさせてしまったり、「あの時、ノっておけば良かった」と後悔した経験も多々あります。
そのため、本人の個性や、精神的な状態によって、受け入れやすい変化や分野に大きな差があるというのも、経験的に理解しているつもりです。
周囲からの提案やお誘いを何度も断っていると、そのうち声を掛けられることもなくなります。
また、失敗を嫌って定番メニューばかりを選んでいると、自分の世界を広げるチャンスすら失ってしまい、脅威もなく安定している代わりに、成長やチャンスに触れることもない、ドキドキやワクワクのない毎日が続いてしまうかもしれません。
コレは、個人的なプライベートだけでなく、ビジネスの場面でも同様です。
アナタのことを思って手を差し伸べてくれているのに、変化を嫌って「酸っぱい葡萄」だと言い続けてしまうと、助けてくれる人や気にかける人を遠ざけてしまい、自分から誰かに呼びかけたところで、返報性を期待することも難しくなってしまいます。
今回は、そんな現状維持バイアスや、イノベーションのジレンマがもたらす弊害、また、なぜそうなりやすいのかといった点について、簡単に解説してみましょう。
過去への信頼が、自分を形作る
現状維持バイアスがなぜ発生するのか、なぜそんなに強固なのか。
それは精神衛生上における恒常性であり、アイデンティティとも硬く結びついている、信念や常識の塊だから。ヒトとして自分のココロを守り、寝る前の自分と起きた後の自分の間に、同一性を維持するために必要な防衛機構です。
ちなみにギリシャ神話でも、死を司るタナトスと睡眠を司るヒュプノスは双子の兄弟神とされ、睡眠と死は隣り合うもの、関連があるものとみなされていました。睡眠という「仮死」を経て、再び蘇る。このサイクルの間で、なぜ同じ自分と認識できるのか。また、「私」とはどこにいるのかは、哲学や脳科学においても、今なお難しいテーマです。
話を元に戻すと、現状維持バイアスが働いたり、コンフォートゾーンに留まろうとしてしまう背景には、自己防衛が関わっているからであり、同じことを繰り返してしまうのは、自然な反応であると言えます。
また、相対性理論や量子力学の発展に貢献したアインシュタインは、「常識とは、18歳までに身につけた偏見のコレクションでしかない」と述べています。つまり、「自分らしさ」やアイデンティティの背後には、それまでの人生で「信頼できる」と思った偏見によって支えられている、とも言えます。
数々の長期記憶や、それによって培われた感覚、「個々の偏見」に対する信仰心が、自己の同一性やアイデンティティを守っているとも言えるでしょう。
裏を返せば、一つ一つの偏見や、これまで信じてきたモノを揺さぶられてしまうと、「自分らしさ」を支えていた土台や柱が崩壊し、アイデンティティの危機に陥る可能性が生じます。
新しいモノを受け入れることで、「今までの自分」が崩壊してしまうかもしれない。
わざわざ、「新しい自分」に適応するコストを支払わなければならない。
何十年も上手くいっていたのに、変えることによってそれを失ってしまったら、どうしよう?
今更そんなリスクは冒せない。だったら、現状維持を優先しよう。
「コンコルド効果」めいた選択も、生き物としてはそんなに間違っているとは思えません。
ただ、人生100年時代。
リスキリングも声高に叫ばれている昨今、無策の現状維持は益々リスキーになっています。
年長者であればあるほど、現状維持バイアスが働いて変化しにくいという傾向を踏まえると、リスキリングとして最初に取り組むべきなのは、多少変化しても揺らがないココロを身につけることや、変化に対して前向きかつ柔軟になるようトレーニングすることなのかもしれません。
周囲に多少譲歩しても「自分」が大きく揺らぐことはないし、多少揺らいだところで狼狽えなくていい。
そういう精神的な柔軟性や逞しさを身につけること。つまり、ココロのリスキリングや鍛錬から手をつけると、さらに効果的じゃないでしょうか……。
リーダーの度量 = ココロの勁さ
精神的な現状維持バイアスは、ビジネスや組織にとっても大きな問題です。
特に、ビジネスオーナーや組織を率いるリーダーのココロが硬くて脆いと、その組織が成長するのは困難でしょう。
「組織はリーダーの器以上に大きくならない」とよく言われますが、この「器」を決めるのは、トップに立つ者のココロの勁さです。どんな変化でも積極的に受け入れ、人や提案を簡単に拒まないこと。それによって「今までの自分」が変化したところで、「自分は変わらない」と肚を括れること。
高い柔軟性と同時に、自分に対して絶対的な信頼も持ち合わせていること。
それはまるで武道の達人のように、穏やかな佇まいながら、覚悟や緊張感を常にまとっているような、心構えです。柔和さと共にどっしりとした安定感も必要です。
従業員の同質性が高く、保守性も高い組織は確かにコントロールしやすく堅牢ですが、変化や万が一のトラブルに弱く、ラガードとしての希少性を活かせているうちは良いですが、それすらも難しくなると跡がありません。
変化の少なさはリソースを温存する上で有利に働きますが、万が一に備えて過度のコストカットに走ってしまうと、新規開拓や次に向けて必要な投資まで渋ってしまい、組織の硬直化に繋がりかねません。筋肉質な体制を目指したつもりが、「頭が硬い社長」や、「話を聞いてくれない上司」の集まりになってしまい、有能な若手から逃げ出す可能性も。
そうなると、人材の入れ替わりが激しい組織や、平均年齢の高い組織になってしまうかもしれません。
リーダーの心の硬さは、組織や人材、思考の柔軟性にも直結します。
組織が固まり、思考まで硬直化してしまうと、高齢者のように運動や変化を益々遠ざけてしまうでしょう。活発さを欠き、運動量が低下してしまえば、熱力学的な死とそっくりになります。
変化を拒んで袋小路に追い込まれれば、あとは滅ぶしかありません。
「角を矯めて牛を殺す」か、あるいは逆か。
死を避けたいなら、ココロを柔らかくするか、変化を選択すべきでしょう。
それでも、リーダーが「よく分からないから」と変化を拒んだり、「既得権益やステークホルダーのために」と提案を蹴って保身に走るようなら、静かに離れて距離を置く。それがお互いのためじゃないでしょうか。
思惑ハズレも受け入れよう
組織のトップや、自分のビジネスとして、上手くコントロールしたい気持ちや、責任やリスクを鑑みてハンドリングしたくなるのもよく分かります。しかしながら、トップやオーナーが許容可能な「想定の範囲内」というキャップをはめてしまうと、どんなに優れた取り組みであっても、思惑通りを超えた結果にはなりません。
たとえ好調であったとしても、自分の制御下を飛び出さないようブレーキをかけてしまったり、事前の計画通りに事が運ばないからと、朝令暮改を繰り返してしまうと、「想定通り」にまでいけば御の字。そこまで到達できずに終わることも、珍しくないでしょう。
これでは、どんなに素晴らしい企画や提案、イノベーションであっても、その本領を発揮することは困難です。「どんな結果になるか分からない」と、始める前から拒絶してしまい、「イノベーションのジレンマ」に陥ることも、珍しくありません。
優秀な社員やパートナーがいても、彼らの優秀さも上限が決められてしまいます。
「リーダーの器」以上の取り組みができないため、組織としても「リーダーの器」以上の成果は上げられないでしょう。
少なくとも、SNSマーケティングでキーワードとなるUGCや、ユーザー同士によるN対Nのコミュニケーションを誘発するためには、公式アカウントからの1対Nのコミュニケーション以外を容認し、自分たちの預かり知らないところで、好き勝手にやり取りされることを許容することが前提となってきます。
こうした種々の取り組みを100%活用するためには、完全に制御したいという気持ちを手放し、コントロールできない部分が出てきても受け入れるといった、柔軟性が求められます。
リーダー自身が、「自分の組織」や「自分のビジネス」といったプライドを捨て、権限だけでなく「受け入れられる範囲」についても委譲していかないと、そのビジネスは良くて現状維持、悪ければ縮小再生産の負のスパイラルに突入します。
先が見通せない怖さに立ち向かい、想定外の破壊的なイノベーションを受け入れる。
その胆力と精神性を、背中で語ること。
組織のため、市場のために部下や仲間を信じること、受け入れることも、リーダーにとって大切な心構えです。
ドリームキラーはアナタかも
業績を上げるために人手を増やしたり、何らかの成果を期待して専門家と手を組んだのに、思ったような成果が出ていないとしたら、それは心のどこかで変化を拒んでいる、アナタ自身に原因があるかもしれません。
自分が受け入れられる「想定内」から抜け出さず、コンフォートゾーンから連れ出そうとする相手には、「酸っぱい葡萄」だと非難して、制御下に置こうとする。理想へ向かって突き進んでいるのに、横槍を入れて妨害する人のことを「ドリームキラー」というのはご存知だと思いますが、自分で自分の可能性を狭め、夢や目標を遠ざけている形になっていませんか?
アナタの力になりたいと思って協力してくれている人に対して、密かに「ここまでで良い」と決め、達成間際になってからそれを切り出されると、あまり良い印象は持たれないでしょう。アナタのためを思い、金銭や名誉を棚に上げて手を差し伸べてくれる人に、「程々で良いから」と支援を途中で打ち切ったり、最初から否定するような振る舞いをすると、自主的に助けてくれる人、声をかけてくれる人は減っていきます。
彼らには、もっと高いポテンシャルがあったり、その先に「本来やりたいこと」があったかもしれません。それは確かに、「アナタの想定」を超える未知の領域かもしれませんが、それ故に周りから一歩抜きん出るきっかけになるかもしれません。
アナタのための小さな挑戦、イノベーションなのに変わることが怖いから拒絶する。
これではいつまで経っても殻は破れないし、個人も組織も成長しないでしょう。
ちなみに、逆にアナタが、年長者や年齢を重ねた大人に何かを提案する場合、本人の許諾や同意を得るために話し合いの場を設けても、その場で断られる可能性は高いでしょう。話としては理解していても、心理的な拒否感があるので、どれだけ言葉を重ねたところで合意形成は困難です。
「角を矯めて牛を殺す」の逆、先に自己完結可能な範囲で実力行使をした上で、生きるか死ぬかを悩む致命傷レベルの心理的な痛みを与えること。勝手に動いて、結果で納得させ、変わらざるを得ない状態に持ち込んだ方が、「イノベーションのジレンマ」を回避するには有効でしょう。
もちろん常識的かつ平和な方法であることが前提の、強硬策です。
自分の中のドリームキラーに打ち勝つには、心の体幹を鍛えること。多少揺さぶられてもブレない軸、レジリエンス力の高い勁いココロを身につけること。譲れない部分、心の中の硬い部分を必要最小限に留めておくと、変化に対して柔軟な受け止め方ができるようになります。
自分がいくつであっても、持論に固執するようであれば「頑固な年寄り」と同じです。
心も体も感性も思考も柔軟に保ち、多少躓いたり転んだりしたところで、すぐにもう一度立ち上がれるよう訓練しておく。
そのためにも、「その組み合わせはあり得ない」と思う創作料理や、今まで遠ざけていたことに挑戦すると、世界も視野も広がるかもしれません。
甘じょっぱいポテトチップスとか、お肉に蜂蜜やフルーツソースなど、振り幅の広い思いつきに、思い切って踊らされてみませんか?
沢山転んで、沢山踊ろう
初めてのことに挑戦すれば、誰しも多少は失敗します。
奇抜な新商品に手を出して、「やめておけば良かった」と損した気分になることもしばしばです。
これは仕事でも同じでしょう。
上手くいくと思って期待した取り組みが大失敗に終わって、散々な目にあったとしても、その過程で新たな出会いや発見、部下の成長が垣間見えたり、転んだだけでは終わらない怪我の功名もあるかもしれません。
挑戦しないと失敗しないし、失敗して転ばないことには、成長も成功も難しい。
何でも拒まれ、否定される職場や関係性より、ちょっとした失敗なら笑い合える、心理的な安全性の高い職場の方が、活気があってお互いに尊重し合えるはず。
成功したいなら、転んでみる。ノリが悪くても、たまにはノって踊ってみる。
イノベーションを起こすために必要なのは、意外とそういう精神論かもしれませんね。
我々は、カスタマーサクセスのために必要だと思ったら、あえて鞭を振るうこともあります。
お金をいただきながら、厳しく向き合うことも厭わないBBNと、Webサイト制作やマーケティングに取り組んでみませんか?
根深い問題を発見し、根本解決を目指したい方がいらっしゃいましたら、お気軽にご相談ください。
アナタのココロを鍛えます。