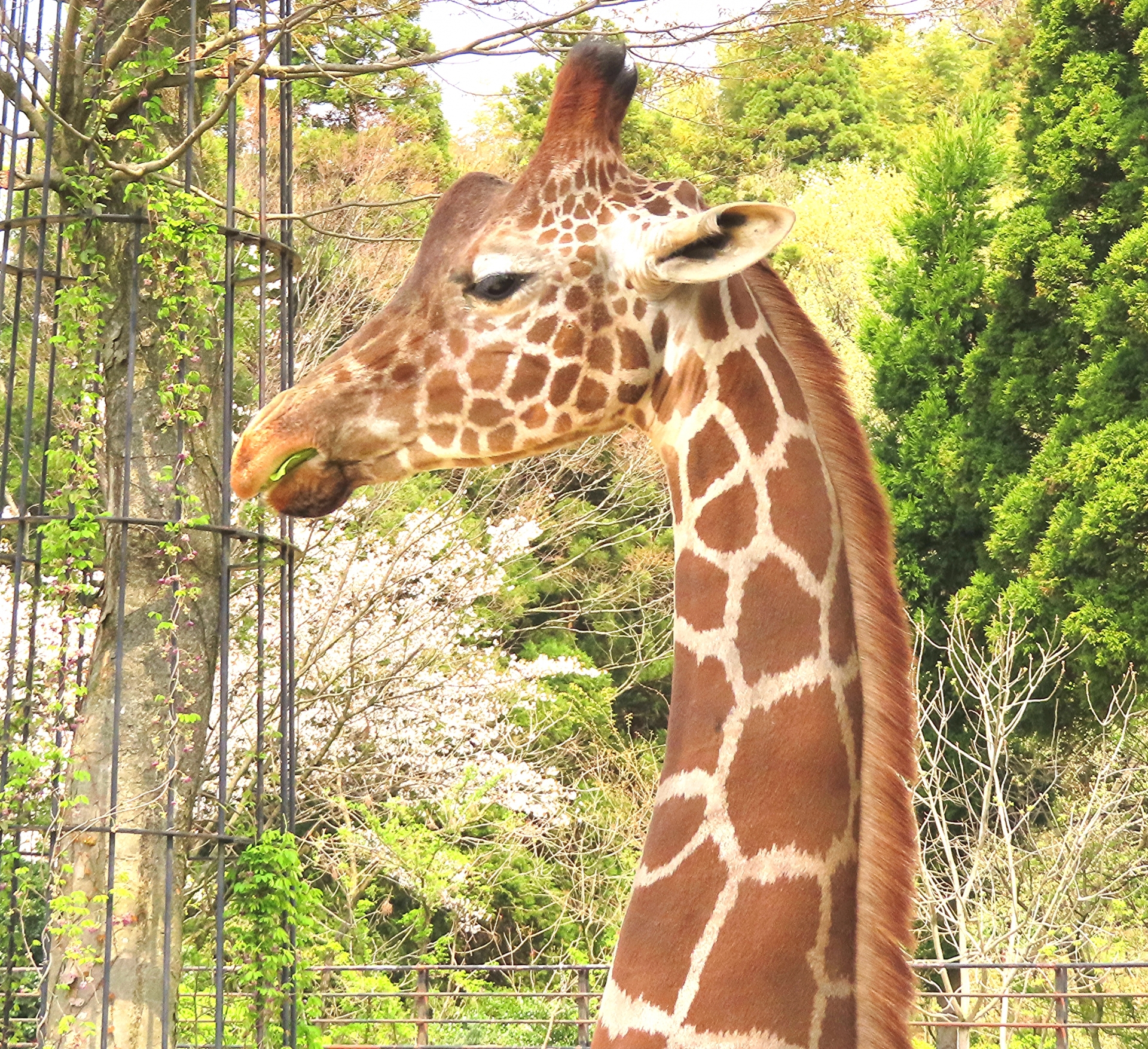前回の『可能性を狭めているのは、アナタ自身かも』(https://bbns.jp/knowledge/1654/)の中で、羽化の話や「常若」にもいつか触れたいと述べていました。羽化については、先週公開したnoteの記事で取り上げました。
『何かを足すな。形を変えろ』
https://note.com/bbns/n/n9b3ce88ce8ec
ということは、今回のテーマは、まだ取り上げていない「常若」です。
進化や変化といった「無常」に対向するような概念として、「変わらずに変える」を貫く「常若」やその意義について、語ってみましょう。
常若 ≒ 恒常性、新陳代謝
「常若」と書いて「とこわか」と読みます。
読んで字の如く、「いつまでも若々しく」というニュアンスです。
常若と切っても切り離せない関係にあるのは、伊勢神宮や出雲大社などの「式年遷宮」でしょう。
参考:『常若(とこわか)=伊勢神宮・式年遷宮にみる和のサステナビリティ』大和総研
https://www.dir.co.jp/report/column/20160406_010798.html
末永く残していくために、材木などの資材や宮大工といった技術継承も含め、形あるものを計画的に作り替えていくという、日本に古くから根付く考え方です。
似て非なる発想としては「テセウスの船」のような同一性のパラドックスもありますが、式年遷宮に関しては肝心のご神体を新しい社殿へ移すので、同一性を疑うことはないでしょう。
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%86%E3%82%BB%E3%82%A6%E3%82%B9%E3%81%AE%E8%88%B9
ただし、解体された方の古材自体は「伊勢神宮の社殿だった物」として再利用されるので、解体後も同一性はしばらく残ります。
常若や式年遷宮というワードだけだと、なんだか縁遠い物だったり、小難しい話に聞こえるかもしれませんが、平たく言ってしまえば、一種の新陳代謝であり、恒常性の発揮、みたいなものです。私たちの身体の中で起きている現象を、神や御神体という見えないものや畏れ多いものが鎮座する場所、社殿というスケールで目撃しているだけ、と言えるかもしれません。
アナタが「私」と認識しているその身体も、皮膚であれば概ね4週間、胃腸の細胞なら長くても1週間程度で作り替えられます。脳や神経は入れ替わらないと言われていますが、アナタが「私」と認識している自我や意識も具体的なモノとしてどこかに存在している訳ではないので、実は自分自身が一種の「テセウスの船」であるとも言えます。
それでも、昨日寝る前の自分と、今朝起きた自分が同一の「私」であると思えるのも不思議な話ではありますが、本題から逸れすぎるのでこの辺りで引き返しましょう。
それでも興味がある方は、『〈わたし〉はどこにあるのか: ガザニガ脳科学講義』(マイケル・S. ガザニガ著 紀伊國屋書店)などを紐解いてみては。
常若や新陳代謝が興味深いのは、同一性の保持や継続という不動性のために、自ら積極的に作り替えるという逆説的なところでしょう。
熱いものは冷たく、整然としているものは乱雑になるという絶対的な力、凄まじい激流に抵抗し、その場へ留まり続けるために、全力で手足を動かすようなものであり、懸命に生命や文化を繋ごうとする姿勢には頭が上がりません。
式年遷宮が終わったから、あるいは代謝のサイクルが一区切り付いたからといって、立ち止まっている暇はありません。すぐに次の作業に取り掛かり、延々と動き続ける。それ故に「無常」にも抗える。変わらずにはいられないなら、積極的に変えて不変や不動を貫くのが「常若」です。
古い細胞が自死しなくなったり、加齢や何かのきっかけで正常な細胞の歩留まりが悪くなると、それを「癌」と呼び、適切に廃棄して置き換えることがいかに大切かも、よく分かりますね。
ちなみに余談ですが、仮にその場で立ち止まったつもりでも、我々は凄まじい勢いで動いています。
赤道付近で時速1700km、日本周辺で時速1500kmにも及ぶ自転する地球に乗り、秒速約30kmという速さで太陽の周りを公転し、太陽系ごと宇宙を駆け巡っています。
地球で生きている以上、「全く動かない」こと、変わらないことは原理的に不可能です。
(参考)
- 太陽系は、天の川銀河の中心部を秒速約240kmで公転
- 天の川銀河も秒速約630kmで宇宙を移動
「移ろわない」は、宇宙規模で無理
アナタがどんなに頑固で腰が重いタイプであっても、地球や銀河系規模で動く以上、季節も天候も変化します。女心も人の社会も、市場の栄枯盛衰も、自然環境も。あらゆるスケールで変化する以上、動ける足を持つのなら、自分から過ごしやすい場所へ移動する他ありません。
人工物も自然も天体規模の事象も、諸行無常。自然淘汰を掻い潜りたければ、盛者必衰を忘れず、「生き延びるため」に、自ら動くべきです。それは、事業活動においても同様でしょう。ただし、積極的に資源を投じて動くことが正解かと言われると、必ずしもそうではありません。
余計な消費を避け、変わらない方が良いこともあると、アンモナイトとオウムガイのような事例が証明してくれます。アンモナイトがいわゆるr戦略、沢山繁殖するスタイル、オウムガイがK戦略、少数精鋭で繁殖するスタイルと言われています。
r-K戦略説
https://ja.wikipedia.org/wiki/R-K%E6%88%A6%E7%95%A5%E8%AA%AC
移ろわず、その場に踏み留まることはほぼ不可能ですが、積極的に変化することもまた、正しいとは限りません。ビジネス的にも動きが遅いタイプをラガードと称したり、市場成長率もシェアも縮小傾向にある分野を負け犬などと呼びますが、変わらないことが功を奏するケースも珍しくありません。
例えば、蓄音機やフィルムカメラなど、多数派が「終わる」と思っていた分野であっても、アナログ盤やシティポップが再評価されたり、フジカラーの「写ルンです」が再注目を浴びたりと、思わぬブームやリバイバル、さらには文化として定着すると言った事例も見られます。
デジタルカメラやスマートフォンの登場によって、フィルムなんて要らないと簡単に切り捨ててしまえば、「昭和レトロ」や加工も修正もできない故の「温かみ」も、存在できなかったかもしれません。
これも簡単には辞めなかったから、起きた事象です。
頑なに「ただ変わらない」は難しくても、不変を貫くことはできる。
どう実践するかは、「常若」が教えてくれるでしょう。
原点回帰、初心、還暦、ラヴェルのボレロ
常若や式年遷宮だけでなく、日本の文化や言葉には元の場所に戻ってくる「循環」や、元通りを意識した「禊」のようなニュアンスが、色んなところに散りばめられています。
生まれた年と同じ十干十二支が一巡する六十歳を「還暦」と言いますが、赤いちゃんちゃんこなどを着せ、「赤ん坊に戻る」のも、その一例でしょう。
「初心忘るべからず」や「原点回帰」も、一旦まっさらな状態に戻した上で、改めて再始動する、今に向き直るというニュアンスが込められています。これは、初心や原点から離れたからこそ意味を持つので、還暦にしても禊にしても、一度離れて世俗に塗れてみる、汚れや傷を負ってみることが欠かせません。
旅に出て知見を深め、経験を積んだ上で「変わらぬ原点」へ戻ってくる。
行って帰ってくる循環、あるいは度々リセットして反復すること、繰り返すことを意識しておくと、「常若」への解像度がより高まるかも知れません。
繰り返しや循環という点で言うと、ラヴェルの『ボレロ』も、一つのヒントです。
スネアドラムは常に同じリズムを叩き続けますし、参加してくる楽器も基本的には同じフレーズを繰り返しますが、音量や音の厚みや徐々に大きく力強いものへ変わっていきます。
単なる繰り返しに見えるけど、中身は全然違う。
それもまた、「常若」に通じる特徴のような気がします。
変わらないこと以外は、積極的に変える
諸行無常で「不変」も「不動」も不可能だからといって、何から何まで全てを変えてしまうと、同一性は完全に失われてしまうでしょう。
常若や式年遷宮のように、変えてはいけない聖域や御神体、受け継がなければならない「守るべきもの」、あるいは「戻ってくる原点」を明確に設定すること。個人であれば「自分らしさ」や「在り方」、事業体であれば「経営理念」や「ミッション」、「パーパス」といった要素を、きちんと言語化しておきましょう。
アナタだけの御神体の見極めや、その設定さえ誤らなければ、それ以外の部分はどんなに刷新、リプレイスしたところで、「同一性」は担保できるでしょう。
環境の変化や技術の発展によって、調達できる資材や導入可能なツール、ノウハウが移り変わっていくことも予想できますが、「変えてはいけないもの」が明確になっていれば、その分、「変えてもいい部分」も明確です。この時、御神体とそれ以外の境界線を間違えないこと。
そこさえ誤らなければ、アナタは安心して、積極的に変化を受け入れられるはずです。
その時々に応じて、最適解を採用する。
積極的に変化を受け入れることによって、受け継ぐものは変化させない。
もし「変えてはいけない」部分に資材や技術も関わるのなら、常に遠い将来を見据えて、継承し続けられるように準備すること。
それもまた、「常若」や「式年遷宮」から見えてくる、「変わらない」ためのヒントです。
遺すために、若々しく
東京商工リサーチによると、「2023年の倒産企業の平均寿命は23.1年」とのこと。
https://www.tsr-net.co.jp/data/detail/1198412_1527.html
製造業は36.3年、サービス業は17.2年、情報通信業は16.0年とのことですが、大手SIerや通信インフラの老舗も含まれていると思うので、いわゆるWeb制作やIT系のベンチャー、スタートアップの場合、長くても15年前後、短ければ5年前後といったところでしょうか。
終身雇用や年功序列の時代ではなくなったとは言え、人生100年時代で事業や企業の方が先に寿命が尽きるのは、やはり気になるところです。
年次の浅い企業や、衰退していく事業には、「遺す取り組み」や「アトツギ」の準備不足が共通しているような気がします。何を残して、何を変えていくか、明確な言語化や仕組み化が欠けていて、ノウハウやスキルの属人化、引き継ぎが不十分な印象が強いです。
サービス業やITなど、完全な属人化を防ぐことは現実的ではありませんし、必ずしも「マニュアル化」やオープンナレッジ、「脱属人化」が適切だとも思いませんが、「遺す」意識や「積み重ね」の欠如は、いつも気になっています。
たかがWeb屋さんなので、そこまで口出しすることはありませんが、「遺す」取り組みや「常若」を実践する上では、非常に親和性が高いのになぁ〜、いつでも声をかけてもらってもいいのになぁ〜、とも思い続けています。
事業や組織をアナタの人生より長く存続させるためにも、「常若」を意識した取り組み、始めてみませんか?
もし、少しでも興味があるのなら、いつでも気軽にお問い合わせください。