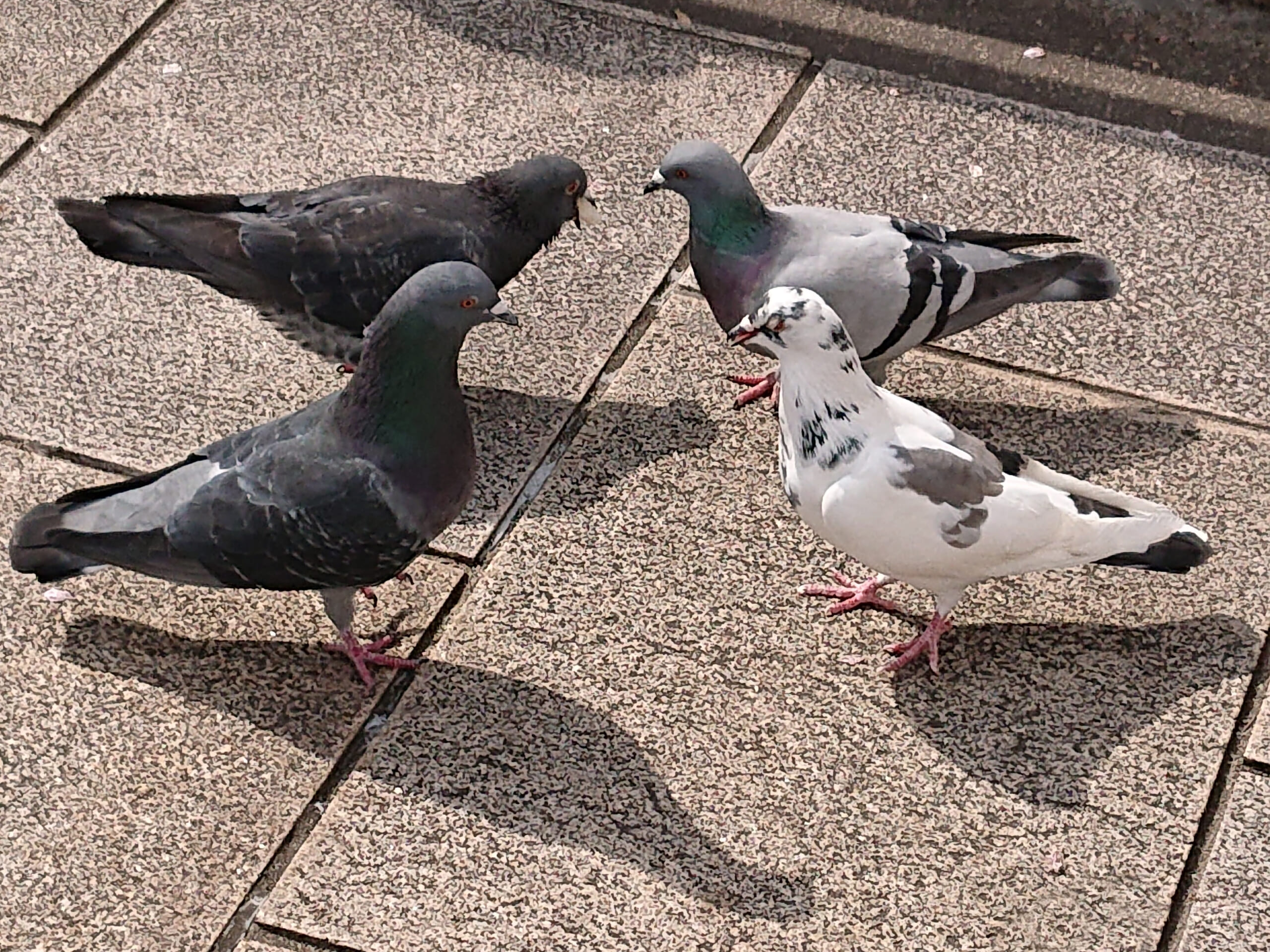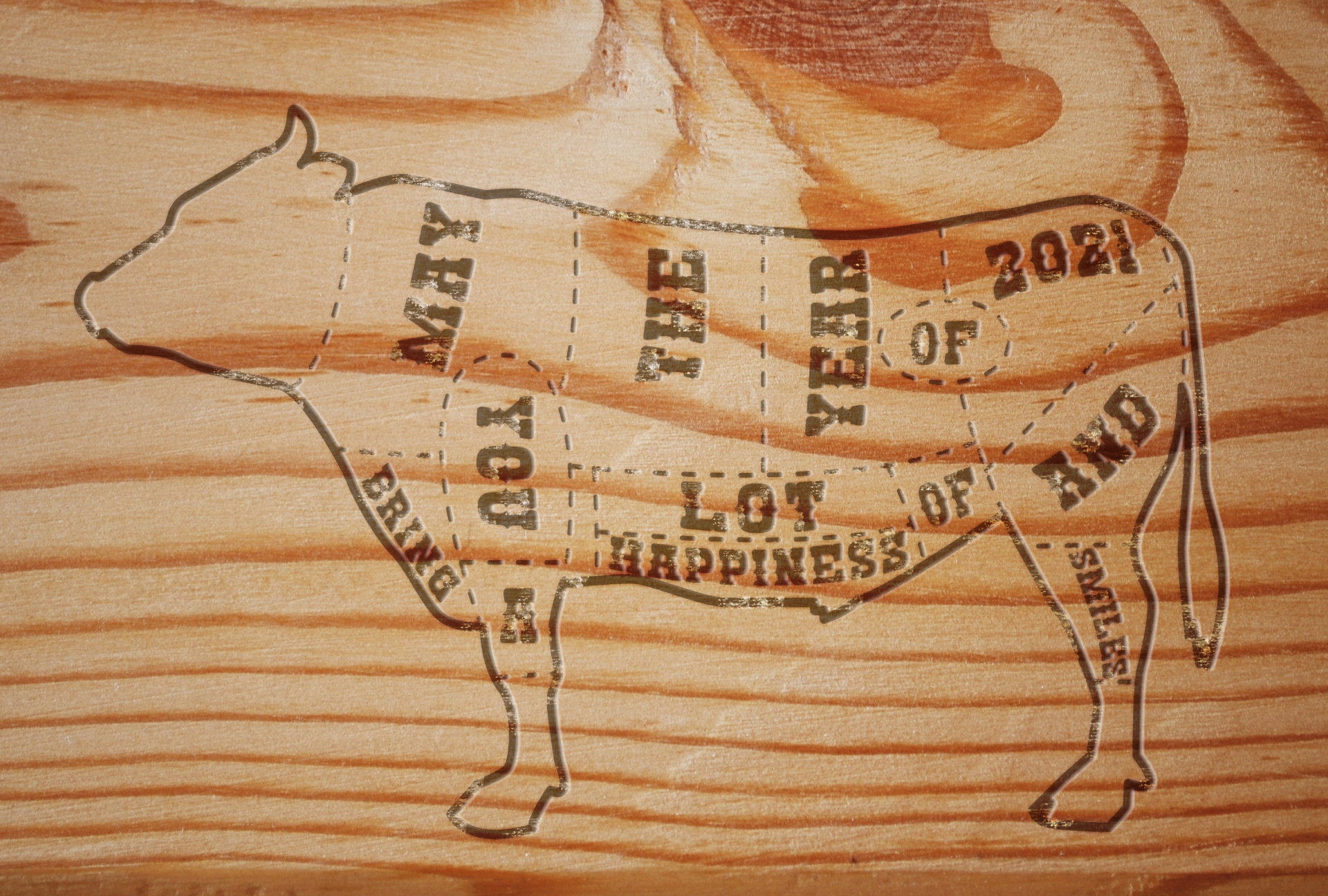ヤード・ポンドに縁遠い日本人には、ピンとこない1マイルは約1.6km。マイルの由来はラテン語で1000を意味する言葉からとのこと。
https://www.nakanihon.co.jp/gijyutsu/Shimada/Computational%20geometry/chapter010302.html
https://blog.goo.ne.jp/h-shiohama/e/546869a6b49e0393f0e4742337483042
1000歩(両足で1歩と数える『複歩』換算)の距離だとか。不動産系で用いられる基準の「徒歩1分は80m」で換算すると20分ぐらい。ゆっくり歩いても30分といったところでしょうか。
野球の世界では豪速球の基準のように言われていた100マイル、日本国内でも忌野清志郎や藤原さくららが歌った名曲は『500マイル(500マイルもはなれて)』。500マイル離れれば確かに郷愁を抱くような距離ですが、徒歩20分で「悠久の」は大袈裟すぎ?
しかし、1マイルの長さがピンとこない日本人でも、「ラストワンマイル」と言われると別の何かを頭の中に思い描くのではないでしょうか。物流業界の方や、ドライバー不足のニュースに関心がある方は耳にされたことがあるでしょうし、通信業界の方も、よく耳にされる用語でしょう。
1マイル、およそ1.6kmの物理的な長さではなく、何かと何かを繋ぐ最後の部分を指す言葉として、「ラストワンマイル」が使われます。色んな部分に「ラストワンマイル」は存在していて、通販や郵便配達では宅配、小売の商流では店頭、さらに言えばレジ周辺も『ラストワンマイル』に該当するでしょう。
通販のプロセスを徹底的にIT化し、物流拠点間の流通も自動運転で人手不足を解消しようとしても、個別の配送や受け取り確認は、どうしても人が担わざるを得ません。スーパーでセルフレジを導入しても完全無人化には至らず、セルフレジ周辺には店員が配置されています。あらゆる分野で「ラストワンマイル」を完全に機械やIT、AIに委ねることは難しそう。それが、現在の共通認識でしょう。
人手が介在する「ラストワンマイル」は、いつまでも縮まらない。空気を閉じ込めたピストンを押し下げても、最後まで抵抗する空気のように。列車に乗って慣れ親しんだ街を500マイルも離れる方が、明らかに遠い印象を持ちますが、この「ラストワンマイル」もまた、簡単には埋められない「隔たり」を持ち続けています。
「冒頭から急に何の話?」と思われそうなくらい、「ラストワンマイル」について長々と話してきましたが、ここからが本題。じっくり触れておかないと、この先の話の意味が変わってしまうので、あえて紙幅(ウィンドウ幅? いや、高さ?)を割かせていただきました。
今回のテーマは、「正確性のラストワンマイル」。
SGEやAI検索が流行り始めた今だからこそ、考えておきたいことを取り上げます。
目次
SGE、AI検索とは?
SGE(Search Generative Experience)は、生成AIを活用し、検索エンジンやGoogleの各種サービスにおいてユーザーの質問に詳細な回答を提供する技術です。詳しくは、Googleの公式発表をご覧ください。
https://blog.google/intl/ja-jp/products/explore-get-answers/2023_08_search-sge
同様にGeminiやPerplexity、X社のGrokなど、生成AIを活用したAI検索が、雨後の筍のように乱立し、専門家でないと追い切れないほどの勢いで増えています。そんな中、Googleはさらに一歩踏み込み、検索に「AIモード」も導入するようです。
こうした変化により、近年すでに価値が低下しつつあった「SEO」、特にGoogleの検索結果画面(SERP)について、「本格的に死んだ」という声もチラホラ見かけるようになりました。
しかしながら、ChatGPTはもちろん、Grokでも「回答は必ずしも正しいとは限りません。重要な情報は確認するように」と注意書きが添えられています。つまり、毎回正確な回答が得られるとは限らないのが現状です。
一方で、Google自身がSGEのアナウンスページを公式発表として用意していることからも分かるように、SEOが「完全に死んだ」とは言い切れません。正確な情報を求める場面では、依然としてSEOが有効であり、不可欠な存在であることがうかがえます。
この状況で、「SEOが無意味だ」とか「AI検索があるから、Webサイトなんて要らない」と本当に言えるでしょうか。答えは明白でしょう。
二次情報、三次情報、SNS上だけの情報は無視されるかも
あくまでも筆者の私見というか偏見ですが、公式が監修して正確性にも責任を持っているストック型の一次情報を掲載したWebサイトよりも、それらをユーザーの投稿や口コミという形で集めたポータルサイトやまとめサイトの方が、今後は衰退度合いが高まるのではないか、と考えています。
どこでも得られる情報なら、生成AIの回答で十分です。わざわざ口コミ系のポータルサイトを見に行く理由はありませんし、固有名詞で検索しても、出所の怪しい情報や「いかがでしたか」の文言に苛立つキュレーションページは、ますます避けられるでしょう。
AI検索で取得しにくそうな、閉じたSNS上の情報も、目一杯発信した所で拡散には限界があるし、検索にも好影響を与えないとなると、例え公式アカウントであっても、フローの一次情報ばかりを発信していても、取り組めば取り組むほど、努力が無駄になる恐れも出て来ます。
正確な一次情報を掲載する場所を、SNSやポータルサイトの外に用意すること。その上で、自分たちが情報の監修者であり、パブリッシャーであるということを、Schema.orgを活用し、著者情報やオリジナルコンテンツの信頼性を示しておかないと、急に「なかったこと」になるかもしれません。
アカウントのBANや、SNSのサービス終了、規約や仕様変更も鑑みると、Webサーバー代やドメイン代、Webサイトの制作費用といった目先の投資をケチってしまうと、積み上げてきた情報資産が、一瞬で失われるリスクがあります。AI検索の時代だからこそ、ますます考えておきたいポイントです。
調べてでも来たい人、どうしても欲しい人を考える
SNSやポータルサイトへ任せっきりで、公式Webサイトを持っていても予約受付サービスのおまけっぽいページしか持っていないタイプの街場の店舗さんや各種病院は、早急に「Webで検索して比較、来店に繋げる人」を意識したWebサイトを作るべきだと考えています。
その段階まで来ている人は来店する意欲やコンバージョンに至る確率が高く、また求めている情報も概ね決まっているので、提示する情報をそれほど考えなくても効果を発揮しやすい傾向にあります。
例えば、飲食店や美容院等であれば、これまで口コミ系サイトやクーポン系サイトで確認できていたことと、営業時間と連絡先、アクセス方法さえ分かれば、あとの詳細は自分たちでSNSをフォローしたり、「お店に行ってから考える」というアクションへ繋げることもできます。
現在、個人的に問題だと考えているのは、口コミ系のポータルサイトや予約受付サービス系のおまけWebサイトの場合、店舗の連絡先や営業時間、場所も誤っているケースがあり、閉業や廃業したところでも、データが残ったままというのもよく見かけます。
お店に行こうと思っている人、これから顧客になる率が高そうな人に対して、この情報提供はよろしくないでしょう。しかしながら、大半の個人飲食店や街場の店舗さんはSNSアカウントまでしか開設しておらず、最近は閲覧数の関係で数日で消えるショート動画ばかりになり、公式アカウントを見つけて覗いてみても、更新が数ヶ月前途絶えているように見えてしまいます。
調べてでも来たい人や、どうしても欲しいと熱望している人に、一次情報としていつでも閲覧可能な店舗情報や連絡先、営業時間が正確に掲載されているだけでも、十分な意味を持ちます。内部SEOが貧弱なWebサイトや使い勝手が悪い古いWebサイトが多いので、イマドキのWebサイトを作るだけで相当優位に立てるでしょう。(レスポンシブは当たり前、表示が早くて待たせない、欲しい情報をさっと提示するのがベスト)
Googleフォームなどの顧客アンケートを通じてエンゲージメントを獲得できたら、Substackなどのメール配信型のコンテンツ配信で、季節限定メニューを通知したり、お誕生日の人に案内を出してリピートを促すこともできますし、OneSignalを使ったプッシュ通知も組み込めば、LINEを使っていない人にも「空席あります」みたいに促すことも可能でしょう。
グルメ系サイトやクーポン系サイトへ広告費を払うぐらいなら、同額ぐらいで利用可能な月額制のサービスでも利用して、Webサイトを作られる方が良いと思います。ただし、投資を回収できるかどうかは、作り手と発注者次第です。
ラストワンマイルは人の手で
どんな業界、どんな場面でも、ラストワンマイルで全てが決まります。
人と人が顔を合わせる現場と、その時の対応次第でサービスの最終的な印象、ブランドや提供元に対する印象も全てが決まるでしょう。飲食店だって、契約の場面だって、そこに居合わせた人の印象や接遇により、総合的な評価や最終結果が大きく変わることもあります。
結局、人と人とが接する場面を微塵も持たずに完結できるビジネスなんて、どこにも存在しません。
便宜上「ラストワンマイル」と表現していますが、もっと手前の段階からその先に待つ「見えない人」に対して、どこまで気を配れるかがポイントです。
AI検索が台頭するからといって、「SEOが死んだ」と感じるのは自由ですが、「正確な情報を求める人がいる」と分かっていれば、提供する側、受け取って欲しい側として何をするべきかは明白です。情報の正確性や、情報そのものの信用性、発信元に対する信頼性の「ラストワンマイル」を人間の手で担保すること。その一言に尽きます。
次の汽車に乗るには一次情報が不可欠
鉄道もバスも、公共交通機関が正確に来る日本の場合、500マイル先へ行くための「次の汽車」が駅に着くのを待とうと思えば、生成AIによる不正確な情報を提示されても困るでしょう。
時間通りに来ないのが当たり前の欧米や、日本以外ならそれでも通じそうですが、日本国内であれば、まずは一次情報や時刻表をチェックするはず。
正確な情報を提供するという「正確性のラストワンマイル」や「信用性のラストワンマイル」を人の手で担保していなければ、500マイル先どころか、乗りたい汽車すら見逃してしまうでしょう。
感傷的な気分になって、思い出を数えたり、見送ってくれる友に格好つけて見せたくても、不可能です。
生成AIが進化して、それっぽい答えを出すようになるからこそ、正しい情報、また自分たちが受け取って欲しい情報は、自分から積極的に提示し、ストックするようにしましょう。500マイル先だってすぐに辿り着けてしまう世の中だからこそ、人の手による「ラストワンマイル」が大切です。
街場の店舗さんにも、BBN
個人経営の飲食店や、珍しいものを取り扱っている商店においては、店舗名や取扱商材等の固有名詞で「調べる」ところまで来れば、そこから先は勝ったも同然でしょう。指名検索で公式Webサイトに流入できれば、流入数は小さくてもコンバージョン率は比較的高めになることが多いです。
BBNでは、ただサイトをご提供するだけでなく、そこから更にどうやって伸ばしていくか、リピート施策は取れないか、顧客アンケートにNPSの項目も組み込んでプロモーションに活かせないか、CRMやマーケティングオートメーションも導入できないかなど、飛び道具も豊富に揃えています。
小規模な店舗さんでも導入しやすい料金体系だと思うので、少しでも興味が湧きましたら、ぜひお気軽にご相談ください。